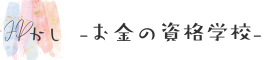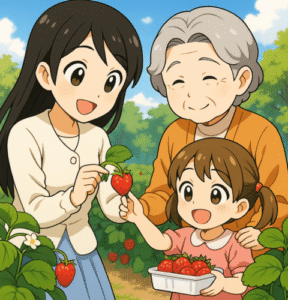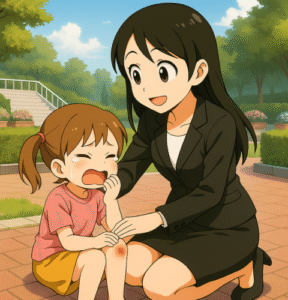FP試験にも実生活にも役立つ💡『FPの業務範囲を整理!やっていいこと・ダメなこと』
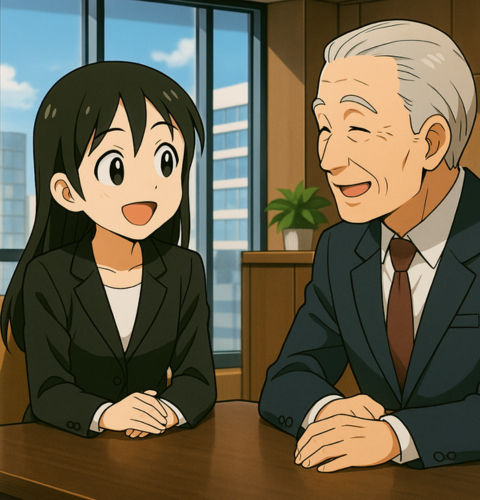

ねえねえ、この前さ、友達がFPの人に確定申告をお願いしたら断られたんだって。
FPってお金のプロなんだから、確定申告も不動産の評価も投資の細かいアドバイスも、ぜんぶやってくれてもよくないのかな~って思っちゃったんだけど…?

気持ちはわかるよ。お金の話って全部つながってるし、まとめて任せられたら楽に感じるよね。
ただね、確定申告の“代理”や不動産の“鑑定評価”、投資の“具体的な指示”っていうのは、法律で特定の士業だけがやっていい仕事なんだ。
FPは“しくみの説明”や“方向性のアドバイス”まではできるけれど、そこから先は専門家にバトンを渡さなきゃいけないんだよ。

えぇ…そんなにダメなこと多いんだね。どうしてなの?なんでなの?

きりちゃんの気持ちはわかるよ。お金のことって全部ひとまとめに見えるし、ひとりに任せられたら便利だよね。
でも、確定申告の代理や不動産の鑑定評価みたいに、法律で“この資格の人だけ”って決まっている仕事があるんだ。
FPは相談や説明はできても、その線を越えることはできないんだよ。
じゃあ今回は、FPの業務範囲を整理して、やっていいこと・ダメなことをわかりやすく解説していくね!
きりちゃんのように「FPってお金のプロなんだから、何でもまとめてお願いできるんじゃないの?」と考える人は少なくありません。
確かに、税金・保険・不動産・投資…これらはすべて家計に関わる分野で、ひとつの専門家に任せられたら便利に見えます。
でも実際には、税務代理や不動産の鑑定評価、法律に関わる相談などは、法律で「この資格を持つ人だけが行える」と決められている大切な仕事です。
FPは制度のしくみを説明したり、方向性のアドバイスを行ったりといった“入口のサポート”まではできますが、その先の専門的な領域に踏み込むことはできません。
とはいえ、これはFPの価値が低いという意味ではありません。
むしろ、幅広い知識を持ったFPだからこそ、相談者の状況を整理し、適切な専門家へつなげることができる大切な存在なのです。
この記事では、そんなFPの業務範囲について「やっていいこと」「やってはいけないこと」をわかりやすく整理して解説していきます。
日本最大級のまなびのマーケット
目次
FPは“家計の案内役” まずはできることを整理しよう
FP(ファイナンシャルプランナー)は、お金のことを「全部まとめて解決する人」ではありません。
どちらかというと、**家計全体を見渡して、いま何が必要なのかを整理し、適切な方向へ導く“案内役”**です。
家計に関わる分野は、税金・保険・投資・住宅ローン・相続・教育費…と本当に幅が広く、どれも少しずつつながっています。
ひとつのテーマだけ深く掘ろうとすると専門資格が必要になりますが、FPはそれらをまとめて俯瞰し、**「どこに課題があるのか」「何から手をつければいいか」**を整理するプロです。
具体的には、次のようなサポートが可能です。
・税金や社会保険などの制度の仕組みをわかりやすく説明する
・家計の現状を整理して、将来の資金計画を一緒に考える
・保険や住宅ローンなどの選び方を一般的な視点からアドバイスする
・必要に応じて、税理士や社労士など専門家への橋渡しを行う
このように、FPは“全部を深くやる専門家”ではなく、
家計の全体像をつかんで方向性を示す総合ガイドのような存在なんですね。

ふむふむ…そういうことなんだね。
じゃあ“私の納税額ちゃんと計算して~”とか“この土地って今いくらなの~?”っていう話になると、そこから先は専門の先生にバトンタッチしなきゃいけないんだ…!

そうなんだ。まとめてお願いできたら楽だし、ひとりの人に全部見てもらえたら安心にも感じるよね。
でも、納税額の計算や土地の評価みたいに、専門知識と責任が必要な部分は、法律で担当できる人が決まっているんだ。
だからFPは無理にやろうとせず、ちゃんとその道の先生につなげることが大事なんだよ。
FP資格継続教育パック
ここから先はNG!FPが踏み込めない“独占業務”とは
FPは幅広いお金の相談に対応できますが、どれだけ知識があっても 踏み込んではいけない領域 があります。
それが、特定の資格者だけが行える 独占業務 です。
この部分を越えてしまうと、FPだけでなく相談者にもトラブルが生じる可能性があるため、線引きを理解しておくことがとても大切です。

FPって独占業務があるわけじゃないんだよね。
だから“これとこれだけがFPの仕事です”みたいな線引きが決まっているわけでもない。
結局のところ、一般の人とできること自体は大きく変わらないんだ。
ただ、家計や税金、保険、資産運用みたいな幅広い知識を体系的に学んで、試験に合格しているという“信用”が乗っかってくる。
だからこそ、相談する側は安心して話ができるし、FPはいろいろな分野をつなぐ“入り口”としての役割を果たせるんだよ。
✅ FPができない主な独占業務
● 税務代理や税金の計算(税理士の業務)
「納税額を計算してほしい」「確定申告を代わりに提出してほしい」といった依頼は、税理士だけが担当できる業務です。
FPは制度の説明まではできますが、計算や代理提出は行えません。
● 社会保険の手続き代行(社労士の業務)
健康保険・年金・労働保険などの手続きを代わりに行うことは、社労士の独占業務です。
FPができるのは制度の仕組みを説明するところまでで、実際の手続きは行えません。
● 不動産の鑑定評価(不動産鑑定士の業務)
「この土地はいくらです」といった価格を確定する評価は、不動産鑑定士だけが行える専門業務です。
FPは一般的な相場を伝えることはできますが、評価額の算定はできません。
✅ FPはどこまで関われるのか
これらの専門的な部分は士業に任せつつ、FPは制度の説明や方向性のアドバイスを行う“家計の案内役”として関わります。
必要に応じて正しい専門家につなぐことが、FPとしてとても重要な役割です。

たしかに~!もしFPがなんでもできるスーパーマンだったら、ほかの士業の先生たちいらなくなっちゃうよね~。

そうそう。ていうかね、全部の士業の仕事を一人でこなせるようにするなんて…
そんなのどの資格よりも難しい“超超超・最難関資格”になっちゃうよ💦
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】
専門家じゃないからこそできる FPの中立で広いサポート
FPには税務代理や手続き代行といった独占業務はありません。
一見すると「専門的な仕事ができないから弱いのでは?」と思われがちですが、実はこの“距離感”こそがFPの大きな強みです。
FPは税金・保険・投資・住宅・相続など、家計全体を横断的に見る立場にあります。
特定の商品や特定の制度に縛られず、相談者の状況を中立に整理し、必要な方向性を示すことができます。
これは、どこか一つの専門に特化した士業には持ちにくい広い視点です。

住宅って一つの話に見えて、実はローン、税金、団信や火災保険、そして家計全体の計画まで、いろんな分野が重なっているんだよ。
それぞれ専門の先生がいるけれど、FPは全体を横断して整理できるから、相談者にとって何を優先すべきかをまとめてあげられるんだ。これがFPの強みなんだよ。

えっ…そんなふうに全部まとめて考えてあげられるの?
ローンも税金も保険も家計のことも…ちゃんとつながりで見て方向を示してあげるなんて、本当にすごいんだね。
なんか急にFPがキラキラして見えてきたよ…。私も今勉強してるし、いつかそんなふうに誰かの役に立てるFPになれたらいいな…がんばろ…!
また、FPは“入り口の専門家”として、相談者の悩みを大まかに分類したり、優先順位をつけたりすることができます。
そのうえで、深い領域が必要なときには、税理士・社労士・不動産鑑定士など、適切な専門家へ確実につなぐことができます。
こうした「つなぐ力」は、家計全体を俯瞰できるFPだからこそ発揮できる価値です。
中立で広い視点を持ち、相談者の状況を整理し、必要な専門家へ導く――
この流れを自然に行えることが、FPの大きな役割と言えます。
お金で失敗する人生はもったいない「お金の教養講座」
FPは“家計の案内役” 正しい理解が価値につながる

今日のお話、すっごいわかりやすかったよ~。
FPって、家計のあちこちを全部まとめて案内してくれるんだね。なんか、私もこんなふうに人の役に立てるFPになりたいな…ってちょっとワクワクしてきたよ。

うん、きりちゃん。その気持ちはとても大事だよ。
FPは専門の先生みたいに深い作業はできないけれど、全体を見て“どこに課題があるのか”を整理してあげられる。
案内役としての役割を正しく理解していると、相談者にとって本当に頼りになる存在になれるんだ。

そうだね。FPが価値を発揮するのは、まさにその“家計の案内役”としての姿勢なんだよ。
自分の業務範囲を理解して、必要なところへきちんとつないでいける。そういうFPこそ相談者を守れるし、信頼されるんだ。
きりちゃんもその調子で一緒にがんばっていこうね!

よし…ますますFP頑張らなきゃって気持ちになってきたよ!もっともっと勉強して、いつか自信を持って“こうですよ”って言えるくらい成長したいな。
よーし、今日からまた気合い入れていくぞ~っ!
きりちゃんのように、FPの役割や業務範囲を正しく理解していくと、FPが“家計の案内役”としてどれほど大切な存在なのかが見えてきます。
FPは何でも代わりに行う専門家ではありませんが、家計全体を横断的に整理し、必要な専門家へ適切につなぐ力が求められます。
この姿勢こそが、相談者にとって安心につながり、FPの価値を高める大きなポイントになります。
また、FPができること・できないことの線引きを理解しておくことは、実務だけでなく試験の学習にも大きく役立ちます。
“どの領域がどの士業の仕事なのか”が整理されていると、試験問題でも迷いにくくなり、実生活でも正しく対応できる判断力が身につきます。
FPの本質は、幅広い知識を武器に、相談者の人生全体を見渡して方向を示すことにあります。
今回の内容が、FPを目指す人にも、すでに学んでいる人にも、そして誰かの役に立ちたいと思う人にも、しっかりと力になるはずです。
FP試験にも実生活にも役立つ“正しい業務範囲の理解”。
これを押さえておくことで、より信頼されるFPへ一歩近づくことができます。
スキマ時間を有効活用できる【オンスク.JP】