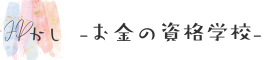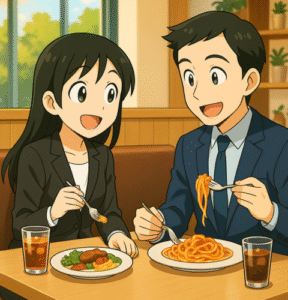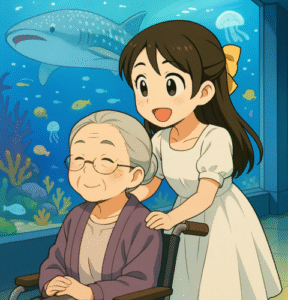FP試験にも実生活にも役立つ💡『宅建士の業務と役割をやさしく整理』


ねえまどくん、宅建士って結局なにができる人なの?
売買とか賃貸に関わるって聞くけど、どこまで任せてもいいのかよく分かんないんだよね、、、
宅建士じゃないとできない仕事ってあるの?

いい質問だね、きりちゃん。
宅建士は、不動産の売買や賃貸のときに、法律に沿って安全に進めるための“専門家”だよ。
とくに代理や媒介みたいな重要な部分を、しっかり任せられる資格なんだ。

そういえばさ、この前わたしが部屋を借りたときに契約してくれたのって、大家さんじゃなくて宅建士さんだったんだよね。
やっぱり一般の人が代理でやってたら“ほんとに大丈夫…?”って不安になるじゃん?
宅建士さんって、あのときめちゃくちゃ頼りがいあったし、なんか急にかっこよく見えてきたよ。もっと詳しく知りたいな〜!

うんうん、きりちゃんその気持ちよく分かるよ。
確かに専門家が間に入ってくれるだけで、不動産の取引って安心感が全然ちがうんだよね。
よし、じゃあ今回は、宅建士がどんな業務をして、どんな役割を持っているのかを分かりやすく解説していくよ!
不動産の売買や賃貸は、人生の中でも金額が大きく、専門用語や法律の知識が必要になる場面が多い取引です。きりちゃんが感じたように、一般の人が「代理で手続きを進めます」と言われても、本当に大丈夫なのか不安になるのは当然のことです。そこで頼りになるのが宅建士という存在です。
実際の現場では、物件を紹介したり内見に案内したりするのは、宅建士ではない一般のスタッフが担当することも少なくありません。営業的な説明や案内業務は資格がなくてもできます。しかし、取引内容に深く踏み込み、法律に基づいた説明や、契約書類への記名押印といった“責任を伴う場面”になると、必ず宅建士が登場します。これは、重要な判断を誤らせないための仕組みであり、消費者を守るための大切なラインでもあります。
専門家が最後にきちんと確認し、“ここから先は法律に基づいて進めます”と説明してくれることで、取引の透明性と安全性が保たれています。不動産取引の不安を取り除くために、宅建士は欠かせない役割を担っているのです。
では次に、宅建士が実際にどのような業務を行い、どんな役割を持っているのかについて、詳しく解説していきます。

ちなみに正式名称は“宅地建物取引士”っていうんだけど、ちょっと長くて読みづらいよね。
この記事では分かりやすくするために、呼び方を“宅建士”に統一して説明していくよ。
スキマ時間を有効活用できる【オンスク.JP】
目次
宅建業者の免許が必要となる業務(売買・交換・貸借の代理・媒介)
不動産の売買や賃貸を「仕事として」扱う場合、まず前提として必要になるのが宅地建物取引業(宅建業)の免許です。
これは、一般の個人が気軽に行うことはできず、法律に基づいた免許を受けた事業者だけが取り扱える専門的な業務です。

ありゃ?ここって宅建士の話じゃないの~?
なんで“宅建業者の免許”のところから説明するの?

宅建士について理解するには、その前提となる“宅建業者ってどんな仕事をしてるのか”を知っておくことが大切なんだ。
宅建士は宅建業者の中で専門的な役割を担当するから、まずは全体の仕組みから順に見ていくよ。
宅建業者が行える取引の中心となるのが、次の4つの業務です。
① 売買の代理
依頼者に代わって、不動産を売買する契約そのものを行うこと。
価格交渉、条件調整、契約締結までを「本人と同じ効力」で遂行します。
② 売買の媒介
売主と買主の間に立ち、双方の条件を調整しながら契約成立をサポートする業務。
いわゆる一般的な不動産仲介はこの媒介にあたります。
③ 交換の代理・媒介
土地や建物を交換する場合にも、代理や媒介として関わることができます。
評価額や差額調整(差金)の交渉など、専門的な判断が必要になる取引です。
④ 貸借(賃貸)の代理・媒介
賃貸物件のオーナーや入居希望者のために、賃貸借契約を代わりに結ぶのが「代理」、
双方の条件調整をして契約成立までサポートするのが「媒介」です。
これらの取引は、金額の大きさや権利関係の複雑さから、トラブル防止や消費者保護の観点で厳格に管理されています。そのため、個人が自由に行えるものではなく、宅建業の免許を受けた事業者だけが取り扱える業務と明確に定められているのです。

私が引っ越すときに、部屋探しとか内見を手伝ってくれたお姉さんって、宅建士じゃないって言ってたんだよね。
ってことは、“宅建業者=宅建士”ってわけじゃないのか~。

いい気づきだね、きりちゃん。
たしかに、内見を案内してくれたスタッフさんが宅建士じゃないことはよくあるし、
“宅建業者=宅建士”というわけでもないんだ。
不動産会社そのものが『宅建業者』で、
その中に専門的な場面を担当する『宅建士』がいる、という仕組みなんだよ。
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】
宅建士はどこに何人置けばいい?宅建業者の設置義務
宅建業者には、不動産取引を適正に行うために事務所ごとに一定数の宅建士を配置する義務があります。これは宅建業法で定められており、「設置義務」と呼ばれています。
まず前提として、宅建業者は
“事務所に従事する者の5人につき1人以上の宅建士を置かなければならない”
とされています。

“5人につき1人以上は宅建士じゃなきゃダメ”って、なんだか選ばれた専門家って感じでかっこいいね!
そんな重要ポジションなら、私も資格とって不動産で働いてみたくなってきちゃったよ~。
こういう“頼られる役割”ってちょっと憧れちゃうんだよね。

その気持ちは分かるよ、きりちゃん。
宅建士は事務所に必ず一定数いなければならない資格だから、現場でも重宝されることが多いんだ。
実際に、宅建士に資格手当を支給している会社も少なくないし、待遇面でも評価されやすい資格なんだよ。
ここでいう「従事する者」とは、その事務所で不動産取引に携わるスタッフ全体を指します。営業担当者だけではなく、受付・事務・案内スタッフなども含まれるため、人数に応じて必要な宅建士の数も変わってきます。
例えば、
・従事者が5人 → 宅建士1人
・従事者が10人 → 宅建士2人
・従事者が13人 → 宅建士3人
というように、5人単位で配置数が増えていきます。
また、宅建業者の本店(主たる事務所)だけでなく、支店・営業所(従たる事務所)にも宅建士を配置しなければなりません。どの事務所でも重要事項説明や書面の記名押印が迅速に行えるよう、全国どこでも同じ基準が求められています。
このような設置義務があることで、不動産会社を利用する人がどの店舗に行っても、法律上必要な説明や確認を宅建士が確実に行える体制が保たれているのです。
FP資格継続教育パック
宅建士が担当する“3つの重要な職務”をわかりやすく整理
宅建業者として不動産取引を行うためには、事務所に一定数の宅建士を置く必要があります。
では、その宅建士は実際にどんな場面で力を発揮するのかというと――
法律上「宅建士だけができる」と定められた、次の3つの重要な職務があります。
① 重要事項説明(重説)
売買や賃貸の契約を結ぶ前に、物件や権利関係、法令上の制限など、取引に影響する大切なポイントを契約者へ説明する仕事です。
ここは宅建士“だけ”が行える独占業務で、契約前の安心材料となる最も重要なプロセスです。
② 重要事項説明書(35条書面)の記名押印
重説に使われる「重要事項説明書」には、宅建士が自分の名前を記入し、押印しなければなりません。
これは、説明内容に責任を持ち、適切に説明が行われたことを証明する役割を果たしています。
③ 契約書(37条書面)の記名押印
売買契約書・賃貸借契約書など、契約成立後に交付される書面にも宅建士の記名押印が必要です。
契約内容に誤りがないか、法律に沿って作成されているかを確認する、取引の最終チェックの場面です。
これらの3つは、不動産取引の安全性と透明性を守るための“最重要ポイント”であり、宅建士が欠かせない理由でもあります。
取引そのものを行うのは宅建業者ですが、取引の核心に触れる場面は、必ず宅建士が責任を持って担当する仕組みになっているのです。

お部屋の紹介や内見の案内は一般のスタッフでもできるけど、最後の“しめ”になる重要事項の説明や契約の手続きは宅建士じゃないとできないんだね。
そんな大事なところを任されてるなんて、かっこよすぎて…ほれぼれしちゃうよ~。

その気持ちわかるよ、きりちゃん。
宅建士は取引の中でも特に大切な“重要事項の説明”や“契約書の最終チェック”を担当する立場だからね。
一般のスタッフには任せられない場面をきちんと支える、まさに専門家としての役割なんだ。
お金で失敗する人生はもったいない「お金の教養講座」
不動産取引は“免許+宅建士”で成り立つ仕組み

なるほど~。不動産取引って、誰でもできるわけじゃなくて“宅建業の免許を持った会社”じゃないとダメなんだね。
しかも、その中で大事な部分は宅建士が担当するって…ほんと、2つがそろって初めて成り立つ仕組みなんだね。

そうだよ、きりちゃん。
取引そのものを扱うのは宅建業者の免許、そして契約前の重要事項説明や書面の記名押印は宅建士。
どちらが欠けても安全な不動産取引は成り立たないんだ。
“免許+宅建士”の組み合わせこそが、取引を正しく支えているんだよ。

まとめると、不動産取引は免許を受けた事業者が全体を運営し、
その中で重要な説明や最終チェックを宅建士が担うことで、安心して契約できる仕組みになっているということだね。
この2つの役割をしっかり押さえておけば、不動産の仕組みがぐっと理解しやすくなるよ。

そっか~!仕組みがちゃんと分かると、不動産ってなんだか難しそうに見えても案外“ルールに守られてる安心な世界”なんだね。
私もこれから不動産を見る目がちょっとレベルアップした気がするよ。
よしっ、次に引っ越すときはもっと上手に選べそうな気がしてきた~!
不動産の売買や賃貸は金額が大きく、専門知識も複雑です。
そのため、取引そのものを扱うには“宅建業の免許”を受けた事業者が必要であり、
さらに契約の核心部分は“宅建士”が担当するという二段構えの仕組みになっています。
宅建業者が代理・媒介を通じて取引全体を支え、
宅建士が重要事項説明や書面の記名押印で内容の正確性と安全性を確保する。
この分業によって、不動産取引が法律に基づき安心して進められるようになっています。
そして、この仕組みを理解することは FP試験にも実生活にも大きなメリット があります。
試験では宅建業法や不動産分野で頻出のテーマですし、
日常の部屋探しや住宅購入の場面でも「誰が何を担当するのか」を知っていれば、
契約前に不安を感じたり、説明不足に気づけなかったりするリスクを減らせます。
たとえば、引っ越しの際に“説明が曖昧なまま契約を進める”といった失敗は、
「ここは宅建士が説明するべき部分だな」と理解しておくだけで防ぐことができます。
知識が自分の身を守ってくれる典型的な分野なんです。
不動産は大きなお金が動く世界ですが、
今回のポイントさえ押さえておけば、必要以上に怖がらずに安心して判断できます。
FP学習でも、普段の生活でも役に立つ知識として、ぜひ覚えておいてくださいね。
日本最大級のまなびのマーケット