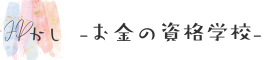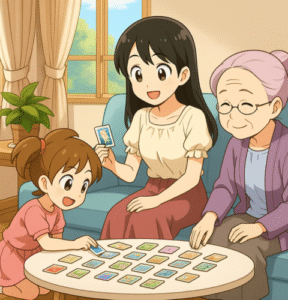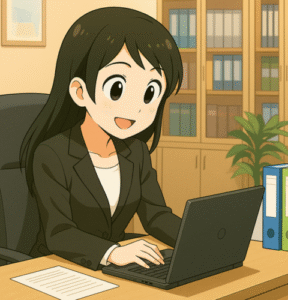FP試験にも実生活にも役立つ💡『保険加入で見落としがちな“告知義務違反”をやさしく解説』
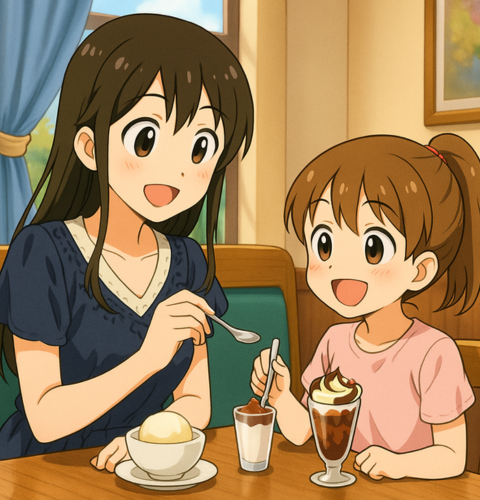

親戚のおじさんね、生命保険に入るときに本当はたばこ吸ってるのに、“吸ってないよ〜”って言おうとしたら、奥さんにすっごく怒られてたんだよ。
でもさ、なんで嘘つこうとしたんだろ…? 正直に言えばいいのに…。

きりちゃん、その気持ちはよく分かるよ。
おじさんも、できれば保険料を少しでも抑えたい…そんな思いがあったのかもしれないね。
でもね、告知は事実どおりに伝えることがとても大切なんだ。後から困ることを避けるためにも、正直に申し出るのが一番だよ。

あ〜なるほど!
確かに、たばこ吸ってない方が病気のリスクも低いし、保険料も安くなるんだね。
でもやっぱり、嘘つくのはよくないよね。
ねえねえ、せっかくだし“告知義務違反”についてもっと詳しく教えてよ〜。

きりちゃんの言うとおりだよ。
たばこを吸っていない方が病気のリスクが下がるから、その分保険料が安くなるのは確かなんだ。
でもね、どんな理由があっても嘘の告知は後で大きなトラブルにつながってしまうんだ。
じゃあ今回は、保険加入で見落としがちな“告知義務違反”について解説していくよ。
生命保険に加入するときの「告知」は、契約内容を正しく成立させるために欠かせない大切な手続きです。健康状態や生活習慣、過去の病歴などは、保険料や保障範囲に直接関わる情報であり、正しく申告することで公平な契約が成り立ちます。
一方で、少しでも保険料を安くしたい、できるだけスムーズに加入したい――。そんな思いから、つい事実とは異なる内容を申告してしまうケースも少なくありません。
しかし、告知内容に誤りがあると、後になって保険金が受け取れない、契約が解除されてしまうといった重大なトラブルにつながる可能性があります。
だからこそ、告知義務の意味や、どこからが「告知義務違反」になるのかを正しく理解しておくことがとても大切です。
それではここから、保険加入で見落としがちな“告知義務違反”について解説していきます。
様々な資格学習が1078円でウケホーダイ!【オンスク.JP】
目次
なぜ“告知”が必要なのか:保険の仕組みから整理
生命保険や医療保険は、多くの人が支払う保険料をもとに、病気やケガが起きた人に保険金を支払う「相互扶助」の仕組みで成り立っています。
そのため、契約者一人ひとりの健康状態や生活習慣などのリスクが、公平な形で保険料に反映されていることがとても重要です。
もし、健康上のリスクが高い人が事実を隠して加入してしまうと、本来より低い保険料で契約できてしまうため、他の契約者との公平性が損なわれてしまいます。これでは、保険制度そのものが成り立たなくなってしまいます。
そこで、保険会社は契約を引き受ける前に、病歴・通院状況・喫煙習慣などの重要な情報を確認し、適切な保険料や加入可否を判断します。
この「正しい判断」を行うために求められるのが、加入者の側の“告知義務”です。
つまり告知とは、加入者と保険会社の双方が安心して契約を結ぶための、基本的で欠かせない手続きなのです。

もしみんなが嘘をついて“めっちゃ健康体です~!”なんて言って保険料を安くしちゃったら、
本当は病気の人が多いのに保険金だけどんどん出ていってさ。
集まってる保険料じゃ全然足りないよ!ってなっちゃって、そんなの保険が続かなくなるよね~。

きりちゃんの言うとおりだよ。
保険は、みんなが保険料を出し合って支え合う“相互扶助”の仕組みで成り立っているんだ。だからこそ、正しい情報をもとに公平に負担することが大切なんだよ。嘘の告知が増えてしまうと、その仕組みそのものが崩れてしまうからね。
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】
告知義務違反になりやすい“よくあるケース”
生命保険・医療保険の加入時には、健康状態などを正しく申告する必要があります。ここでは、特に見落としやすく、告知義務違反になりやすい代表例を4つに絞って整理します。
① 喫煙を隠す(ノンスモーカー扱いにしたいケース)
喫煙はリスクに直結するため、保険料が大きく変わります。
吸っているのに“吸っていない”と申告するのは典型的な違反です。
② 過去の病歴・通院歴を申告しない
「もう治ったから」「昔のことだから」と自己判断で告知しないケースは多く、違反につながりやすい項目です。
③ 服薬中であることを隠す
血圧・コレステロール・精神科の薬など、日常生活に支障がなくても告知が必要な薬は多くあります。
④ 再検査・経過観察の指示を伝えない
治療をしていなくても、“再検査をすすめられた”こと自体が重要な医療情報であり、申告が必要です。
この4つは特にトラブルに発展しやすい部分です。
自己判断で省略せず、気になる項目は必ず確認しておくことが大切です。

へぇ〜、こうして見ると告知で気をつけなきゃいけないことって意外と多いんだね~!
自分では大したことないって思ってても、保険会社にとっては大事な情報になるんだなぁ。

そうだね、本人にとっては小さなことでも、保険会社がリスクを判断するうえでは、とても重要な情報になるんだ。
だからこそ、告知は“正しく伝える”ことが大切なんだよ。
FP資格継続教育パック
告知義務違反があるとどうなる?契約への影響を整理
告知義務違反があると、保険契約には大きな影響が生じます。
一見小さな告知漏れでも、保険会社の判断にとって重要な情報であれば、加入後でも問題になる可能性があります。ここでは、具体的にどのような不利益が起きるのかを整理します。
① 保険会社が契約を解除する場合がある
告知内容が事実と異なっていたり、重要な情報が省かれていたりすると、
保険会社は契約を“解除”できる制度があります。
契約後であっても、告知が不適切であれば「契約をなかったことにする」対応がとられることがあります。
さらに、この解除には 使える期間=解除権の期限 が定められています。
- 保険会社が告知義務違反を知った日から1か月以内に行使しなければならない
- 契約から5年が経過すると、原則として解除できない
この「1か月」と「5年」という期限は、
解除がいつまでも可能だと契約が不安定になるための、安全弁のような役割を持っています。

それにしても、“1か月以内に行使しなきゃいけない”って聞くと、えっ、短っ…!
もうちょっと猶予あってもよくない~?って思っちゃうよ。

保険会社はリスクのプロだからこそ、告知内容に問題があるかどうかは早い段階で把握できるように体制が整っているんだ。
だから“分かったならすぐに判断しなさい”という短い期限が設定されているとも言えるね。
もちろん、これは契約者を守るための仕組みでもあるんだ。
もし保険会社が長いあいだ解除できる状態にしていたら、契約者はずっと不安なままだからね。
だから、実務的な意味と契約者保護の両方の理由があって、1か月という期限が決められているんだよ。
② 保険金が支払われない可能性がある
契約が解除されると、当然ながら保険金は受け取れません。
長く保険料を支払っていても、告知の不備によって請求時にトラブルになるケースがあります。
③ 故意だけでなく“うっかり”でも問題になることがある
悪気のある嘘だけが違反になるわけではありません。
「もう治ったし大丈夫と思った」「大したことないから言わなくていいと思った」
という自己判断の省略でも、重要なことであれば違反になります。
④ 契約全体の信頼性が揺らぐことにつながる
告知義務は、加入者と保険会社がお互いに正しい情報をもとに契約を結ぶための仕組みです。
告知が不正確だと、契約そのものの信頼性が損なわれ、後のトラブルの原因になります。

えぇ~、“うっかり”でも違反になっちゃうことがあるんだね~!
悪気がなくても大事なことを言い忘れたらトラブルにつながるって、あらためて気をつけなきゃって思ったよ。
それに、契約の信頼性が揺らぐっていうのもすごく分かるなぁ。
お互いちゃんと正しい情報を出し合わないと、安心して保険に入れないもんね~。

そうだね、きりちゃん。
告知って“うっかり”でも大切な情報が抜けてしまうと、契約そのものに影響が出てしまうことがあるんだ。だからこそ、少しでも迷うことがあれば申し出ておくのが安心なんだよ。
そして、保険の契約はお互いの信頼があってこそ成り立つものなんだ。
正しい情報を伝え合うことで、安心して保障を受けられる土台ができるんだよ。
お金で失敗する人生はもったいない「お金の教養講座」
まとめ:告知義務を正しく理解して安心の保険加入を

今日のお話で、告知ってただの“質問に答えるだけ”じゃなくて、安心して保険に入るための大事なステップなんだって分かったよ~。
うっかりでもトラブルになることがあるって知れて、すごく勉強になったよ!

告知は契約者と保険会社が公平に支え合うための仕組みなんだ。
正しい判断をしてもらうためにも、事実をきちんと伝えることがとても大切なんだよ。
告知義務を理解しておけば、加入後の安心にもつながるからね。

2人ともよく理解できているね。
告知義務は、トラブルを防ぎ、安心して保障を受けるための基本になる部分なんだ。
大切なのは“迷ったら伝える”こと。正しく告知しておけば、保険はきちんと役割を果たしてくれるよ。
これからも、安心できる保険選びのために一緒に学んでいこう!
生命保険や医療保険に加入する際の「告知」は、契約内容を公平に保ち、安心して保障を受けるための大切な手続きです。たとえ小さなことに思えても、健康状態や過去の病歴は保険会社の判断に影響する重要な情報であり、正しく伝えることでトラブルを未然に防ぐことができます。
告知義務違反には、喫煙の虚偽申告や通院歴の隠蔽、服薬中であることの申告漏れなど、日常の中で見落としやすいケースも多くあります。また、契約後に発覚すれば、保険金が受け取れなかったり、契約そのものが解除される可能性もあります。
だからこそ、迷う項目があれば自己判断せず、その都度確認する姿勢が大切です。
告知義務を正しく理解し、正確に伝えることは、将来の安心を確実なものにする第一歩です。
今回の内容は、FP試験の学習にも、実際の保険加入にもそのまま役立つ大切な知識です。
ぜひ押さえて、より安心できる保険選びに活かしてください。
顧客満足度95%の保険相談なら保険マンモス