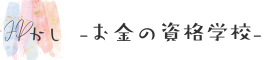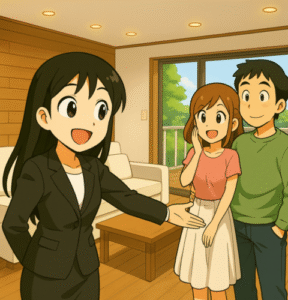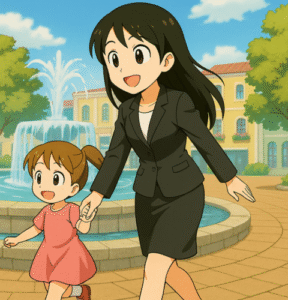FP試験にも実生活にも役立つ「遺留分とは?最低限の取り分を守る制度」
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】


相続のときって遺書が優先されるのはわかるけどさ、、、
もし『配偶者や子どもには一切あげない!最後まで可愛がってくれた孫に全財産あげる!』なんて書かれてたら、
それも優先されちゃうの?だって遺書って亡くなった後じゃないと見られないでしょ?
『えぇー!もらえると思ってたのに!なんてこと書いてんだー!』ってならない?

なるなる、その気持ち。
遺言は基本的に亡くなった人の意思が優先されるけど、、、
配偶者や子どもには“遺留分”っていう最低限の取り分が法律で守られてる。
だから『全部孫に!』って書かれてても、遺留分が侵害されてれば請求できるんだ。

おお!そんな法律があるのか、、、!
もしもの時に備えて、誰がどのくらい遺留分を請求できるのかって、ちゃんと知っておいた方がよさそうだね。
具体的な割合とかも教えてー!

そうだね、知っておくと“もしも”のときに損しないし、家族間のトラブルも防げるよ。
じゃあ今回は『遺留分とは?』をテーマに、最低限の取り分を守る制度について解説していこう。
FP試験にも実生活にも役立つ内容だから、しっかり押さえていくよ!
相続は、亡くなった方の意思を尊重することが大前提です。
しかし、もし配偶者や子どもなどの近い家族に一切財産が渡らないような遺言が出てきたらどうでしょう
「そんなことってあるの?」「私たちは何ももらえないの?」と驚いたり、不安になったりしますよね。
こうしたときに役立つのが「遺留分」という制度です。
これは、法律で定められた“最低限の取り分”を保証する仕組みで、遺言や生前贈与によって不当に取り分が減らされても、一定の範囲で請求することができます。
この制度を知っておくことで、例えば
- 偏った遺言によって自分の取り分がゼロにされそうなとき
- 生前贈与によって財産がほとんど減っていたとき
といった場合に、自分や家族の権利を守ることができますし、感情的なトラブルを少しでも減らすことにもつながります。
それでは今回は、この「遺留分とは?最低限の取り分を守る制度」について、詳しく見ていきましょう。
遺留分とは?相続で守られる最低限の取り分
遺留分とは、配偶者や子どもなど特定の相続人に保証されている「最低限の相続分」のことです。
亡くなった方が遺言で「全財産を特定の人に相続させる」と定めていても、この遺留分を侵害する内容であれば、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」という手続きを通して、その分を取り戻すことができます。

へえー、遺言で『子どもには1円もやらん!』とか書いてあっても、
ほんとに最低限はちゃんともらえるように請求できるの?
そういうのって遺言よりも優先される仕組みなの?

そう、遺言よりも優先される“最低限の取り分”が遺留分なんだ。
配偶者や子どもは、たとえ遺言でゼロにされても、侵害された分を遺留分侵害額請求で取り戻せる。
だから『1円もやらん!』って書かれていても、法律でちゃんと守られてるんだよ。
この制度の目的は、被相続人の意思を尊重しつつ、残された家族の生活や権利を守ることです。
遺言や生前贈与によって財産が極端に偏ってしまうと、配偶者や子どもなどの生活基盤が失われるおそれがあります。遺留分は、こうした不公平を防ぎ、最低限の生活保障を確保する役割を担っています。
遺留分が問題となるのは、主に以下のような場合です。
- 偏った内容の遺言が残されていたとき
- 生前贈与によって相続財産が大幅に減っていたとき
つまり遺留分は、「亡くなった方の意思」と「残された家族の生活」のバランスをとるための、最後のセーフティネットと言えます。

すごい!そんな仕組みがあるならちょっと安心だね。
遺産が全くもらえないと生活が厳しいっていう場合でも、
ちゃんと最低限は守られるってことなんだねー。

まあ、そもそも『相続させない』なんて遺言が出てくる時点で、家庭の状況どうなってんだ…
とはちょっと思うけど、、、
それでも法律は感情抜きで“最低限の取り分”を守る仕組みを用意してる。
だから、たとえゼロにされても遺留分侵害額請求で取り戻せるんだ。
遺留分の権利者と割合の基本ルール
遺留分を請求できるのは、誰でも自由にできるわけではなく、民法で明確に定められた特定の相続人だけです。
これは、相続人のすべてに一律で権利を与えると、相続の自由が大きく制限されてしまうためであり、法律は「生活保障の必要性が高い近しい家族」にだけ、遺留分を認めています。
そのため、対象となるのは配偶者や子ども、直系尊属など限られた範囲にとどまり、それ以外の親族や友人、兄弟姉妹などは遺留分の請求権を持ちません。
- 配偶者
- 子ども(代襲相続した孫を含む)
- 直系尊属(父母や祖父母など)
兄弟姉妹には遺留分がありません。たとえ遺言で取り分をゼロにされても、遺留分を請求することはできません。

へえー、でもなんで兄弟姉妹は遺留分ないの?
兄貴の遺産目当てだったのにー!とかっていう人いそうなのに。
なんかちょっと不公平な感じもしない?

まあ正直、兄弟の遺産なんか最初からあてにすんなって話なんだけど。
法律的にも兄弟姉妹は“生活保障の必要性が低い”とされてるから、遺留分はなし。
配偶者や子ども、直系尊属だけが最低限の取り分を守られるようになってるんだ。
遺留分の割合(全体に対して)
- 相続人が配偶者や子どもを含む場合:全財産の 1/2
- 相続人が直系尊属のみの場合:全財産の 1/3
この割合を**「基礎財産 × 遺留分割合 × 各人の法定相続分」**という計算式で求めます。
基礎財産には、生前贈与や特定の条件を満たす贈与分も含まれる点がポイントです。

あら、直系尊属って取り分ちょっと少なめなんだね。
育ててくれた親なのになんでー?
なんか子どもや配偶者より大事にされてない感じがするよ?

直系尊属は、すでに自分で生活の基盤を持っていることが多いからだね。
配偶者や子どもほど生活保障の必要性が高くないと考えられていて、その分遺留分も少なめになってるんだ。
簡単な例
財産総額 6,000万円、相続人は配偶者と子ども1人の場合
- 遺留分割合:全体の1/2 → 3,000万円
- 配偶者の法定相続分は1/2 → 遺留分は1,500万円
- 子どもの法定相続分も1/2 → 遺留分は1,500万円

こうして計算してみると、、、
もらえるのって全体の半分の、さらにそのまた半分なんだね。
なんか思ってたよりもずっと少なくなっちゃうもんだなぁー。

そうそう、遺留分ってまさにバランスなんだよ。
残された家族の生活も守りつつ、亡くなった本人の意思もできるだけ尊重する。
どっちかに偏りすぎないように調整したのが“最低限の取り分”ってわけだ。
遺留分は“もしも”のときの最後のセーフティネット

なるほどねー、遺留分ってゼロにされても最低限は守ってくれるんだね。
もしものときにこれ知ってるだけで、だいぶ安心できそう!

そうだね。家族の生活を守ると同時に、亡くなった本人の意思もできるだけ尊重する制度だ。
だからこそ“最後のセーフティネット”って呼べるんだよ。

うん、知っておくだけでトラブル回避や損失防止につながります。
今回学んだポイントを押さえて、相続の場面でも落ち着いて判断できるようにしておきましょう。

よーし、これで相続のことちょっとは自信ついたかも!
もしもってときも、知ってるだけで全然気持ちが違うもんね。
なんか前より相続の話も怖くなくなってきたー!
| 相続人の組み合わせ | 遺留分割合(全体) | 遺留分を請求できる人 |
|---|---|---|
| 配偶者+子ども | 全体の1/2 | 配偶者、子ども(代襲相続した孫を含む) |
| 配偶者+直系尊属 | 全体の1/3 | 配偶者、直系尊属(父母や祖父母) |
| 兄弟姉妹のみ | ―(遺留分なし) | 兄弟姉妹には遺留分は認められない |
今回の内容をおさらいすると、遺留分とは配偶者や子ども、直系尊属といった限られた相続人に認められる、法律で保障された“最低限の取り分”のことです。
遺言や生前贈与によって取り分が極端に減らされた場合でも、この遺留分が侵害されていれば、遺留分侵害額請求によってその分を取り戻すことができます。
大切なのは、誰が権利を持っているのか、全体に対してどのくらいの割合が認められているのか、そしてどうやって計算するのかを正しく理解しておくことです。
これらを知っていれば、偏った遺言や不公平な財産分けに直面しても、自分や家族の生活を守るための具体的な行動がとれます。
また、遺留分は残された家族の生活を保障する一方で、亡くなった本人の意思もできるだけ尊重するという、相続制度における重要なバランスの役割を担っています。
この仕組みを理解することで、単に“取り分を守る”というだけでなく、相続全体の流れや背景を冷静に判断できるようになります。
まさに「遺留分とは?相続で守られる最低限の取り分」という今回のテーマは、FP試験にも実生活にも直結する知識です。
学んだポイントをしっかり押さえて、“もしも”のときに慌てず落ち着いて行動できるよう、今から準備しておきましょう!
記事を読んでいただき、ありがとうございました!
「FP資格の勉強を始めたいけど、どこから学べばいいの?」という方には、
日本FP協会認定の講座が受けられる【資格対策ドットコム】が安心です!
初心者でも提案書作成までしっかりサポートしてくれるので、独学に不安がある方にもおすすめです!
FP資格継続教育パック