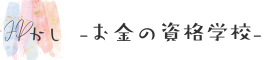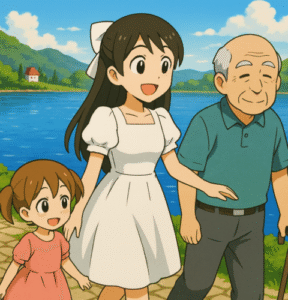FP試験にも実生活にも役立つ「保険法と保険業法の違いをわかりやすく解説」
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】

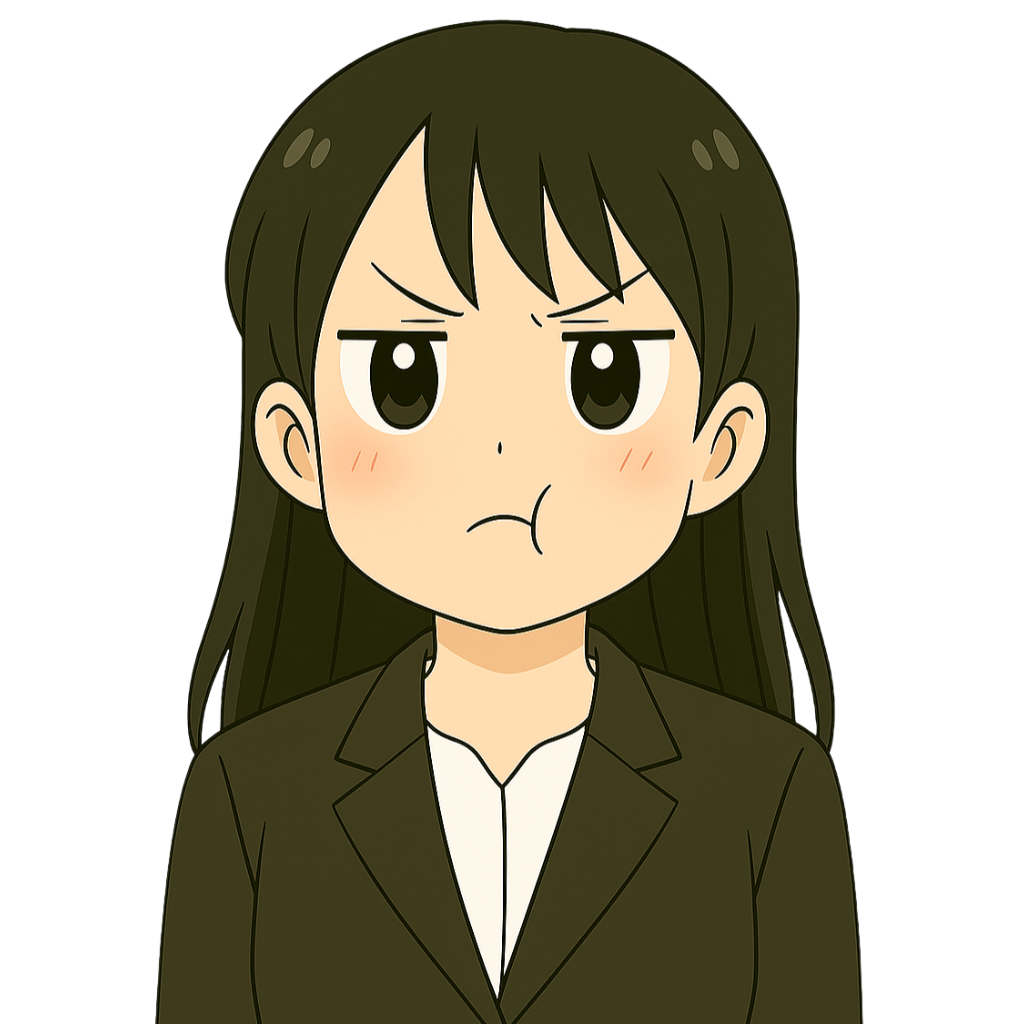
うう~、、、法律ってほんとややこしい!『保険法』とか『保険業法』とか、名前似すぎでしょ!どっちかにまとめてくれたらいいのに~!

確かに、名前が似ててややこしいよね。でも、役割ははっきり分かれてるんだ。
保険法は“契約”のルール、保険業法は“会社”のルール。
つまり、契約者と保険会社の関係を見るのが保険法、
保険会社の運営を管理するのが保険業法ってこと。

うわ~!ますますわからなくなってきたー!契約?運営?ルール?え、なにそれ~!?
もう全部“ほけんのルール”でいいじゃん~!!

きりちゃん、落ち着いて大丈夫だよ。たしかに、言葉だけ見ると混乱しちゃうよね。
でも、それぞれ“誰のためのルールか”を意識すれば意外とスッキリするんだ。
よし、じゃあ今回は保険法と保険業法の違い』をわかりやすく解説していくよ!
きりちゃんの言うとおり、「保険法」と「保険業法」は名前がとてもよく似ていて、混乱してしまいますよね。
実際、FP試験の学習をしている方の中でも、この2つの違いが曖昧なままになっていることは少なくありません。
それに、「契約のルール」「会社のルール」と言われても、最初はなかなかイメージしづらいと思います。
ですが、それぞれが“誰のためのルールなのか”という視点を持つだけで、ぐっと理解しやすくなります。
今回は、保険法と保険業法の違いについて、FP試験にも実生活にも役立つ形で、わかりやすく解説していきます。
保険法とは?契約者と保険会社の関係を定める法律
保険法は、「契約者」と「保険会社」の間で結ばれる保険契約のルールを定めた法律です。
たとえば、保険に申し込むときの手続きや、保険金を請求するときの流れ、契約が解除になる条件などが、この保険法によって定められています。

ふむふむ、、、つまり、保険に入るときとか、保険金をもらうときのルールを決めてるのが保険法ってことか~!

そういうこと。保険契約に関する基本的なルールは、全部この保険法で決まってる。
保険会社が好き勝手に契約内容を変えたり、保険金を払わなかったりしないようにするための仕組みでもあるんだ。
もともとは民法の一部として扱われていましたが、保険特有の事情を反映するため、2010年に独立した法律として施行されました。
そのため、民法の原則をベースにしながら、保険契約に特有のルールが盛り込まれているのが特徴です。
✅ 保険法で定められている主な内容
- 保険契約の成立・失効・解除
- 告知義務や保険金支払いのルール
- 保険金請求の時効
- 契約者・被保険者・受取人の関係 など

『保険金請求の時効』について軽く説明すると、
たとえば事故から2年後に“保険金ください”って言っても、保険法では3年以内なら有効。
つまり、保険会社が“もう払いません”って言ってきても、時効じゃなければ支払う義務がある。

なるほど~!3年以内ならちゃんと請求できるんだね!
よかった~、それならちょっと安心かも!いいね、それ!
この法律を理解しておくことで、保険に加入する際やトラブル時に「契約者としてどんな権利と義務があるのか」を正しく把握できるようになります。
保険業法とは?保険会社の運営ルールを定める法律
保険業法は、保険会社が健全に運営されるようにルールを定めた法律です。
対象となるのは「契約者」ではなく、あくまで「保険会社」や「保険募集人」などの側。
契約そのものではなく、保険会社の経営・商品販売・財務管理などに関するルールが中心です。

そっか、この保険業法って、保険会社のルールなんだよね。
じゃあ、、、私たちお客さん、つまり契約者はあんまり出てこないのか~。

そう。あくまで“保険業”のための法律だからね。
契約者の話じゃなくて、会社側の管理やルールを決めてるんだ。
たとえば、保険会社が事業を始めるためには金融庁の免許が必要で、その後も定期的な報告や監督を受ける必要があります。
また、保険募集人の資格や行動ルール、ソルベンシー・マージン比率などの健全性の指標も、この保険業法によって定められています。

えっ、保険会社って勝手に始めちゃダメなんだ!?
しかも金融庁に報告まで!?
なんか思ったよりガチガチに管理されてるんだね~、、、!

そう。保険って万が一に備えるものだから、いい加減な会社にやらせるわけにはいかないんだ。
だからこそ、厳しいルールで運営を監督して、契約者が安心できるようにしてるってわけ。
では、実際に保険業法ではどのようなことが定められているのか、代表的な内容を確認してみましょう。
✅ 保険業法で定められている主なルール
- 保険会社の設立・事業開始には金融庁の免許が必要
└ 無許可営業は禁止。登録制ではなく「免許制」で厳格に管理されている - 経営の健全性を保つためのルール(ソルベンシー・マージン比率など)
└ 将来の保険金支払いに耐えられるだけの余力があるかを定期的にチェック - 保険募集人の資格・登録・行動ルール
└ 不適切な勧誘や虚偽説明などを防ぐため、募集活動にも明確なルールがある - 商品審査・報告義務・監督命令など、契約者保護のための体制整備

なるほど~!
保険って、将来の“もしも”に備えるすごく大事な商品だからこそ、
こうやって会社の運営までしっかりルール化されてるんだね~!
保険法と保険業法、それぞれの役割を正しく理解しよう

うん、なんとなくだけど、2つの法律の違いがわかってきた気がする!
保険法は“契約者のためのルール”、保険業法は“保険会社のためのルール”、だよね?

そう。視点が違うだけで、どっちも“保険という仕組み”をちゃんと機能させるために必要な法律なんだ。
だから片方だけじゃなく、両方セットで理解しておくといい。

2人ともいいまとめだね。
FP試験でも実生活でも、“契約のルールか、運営のルールか”という視点で整理すれば、混乱せずに覚えられるはずだよ。
これから保険に関する学びを深めていくうえでも、大切な土台になる知識だね。

なるほどね~!最初はごちゃごちゃだったけど、ちゃんと違いがわかってくるとスッキリするね!
なんかちょっと保険のこと、得意になれそうな気がしてきた~!
| 項目 | 保険法 | 保険業法 |
|---|---|---|
| 対象 | 契約者と保険会社の関係 | 保険会社や保険募集人の運営 |
| 内容 | 契約の成立・解除、保険金の請求、告知義務など | 免許制度、健全性のルール、募集人の規制など |
| 主な目的 | 契約者の権利保護 | 契約者の間接的保護と業界の健全化 |
| 管轄 | 裁判所(民事) | 金融庁などの行政機関 |
保険法と保険業法は、どちらも「保険」という仕組みを支える重要な法律ですが、
それぞれの役割や視点には明確な違いがあります。
保険法は、契約者と保険会社のあいだで交わされる保険契約のルールを定める法律。
一方、保険業法は、保険会社や保険募集人の業務運営を管理・監督する事業側のルールを定めた法律です。
この2つをしっかり区別して理解しておくことで、FP試験にも実生活にもきっと役立つ知識になります。
安心して保険と向き合えるように、法律のしくみも味方につけていきましょう!
記事を読んでいただき、ありがとうございました!
「FP資格の勉強を始めたいけど、どこから学べばいいの?」という方には、
日本FP協会認定の講座が受けられる【資格対策ドットコム】が安心です!
初心者でも提案書作成までしっかりサポートしてくれるので、独学に不安がある方にもおすすめです!
FP資格継続教育パック