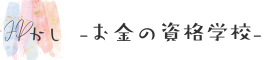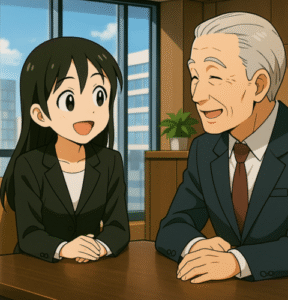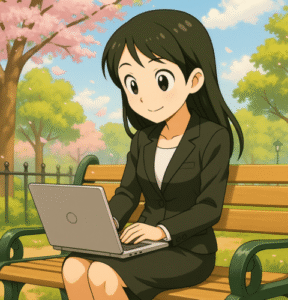FP試験にも実生活にも役立つ💡『保険料はどう決まる?3つの予定率をやさしく整理』
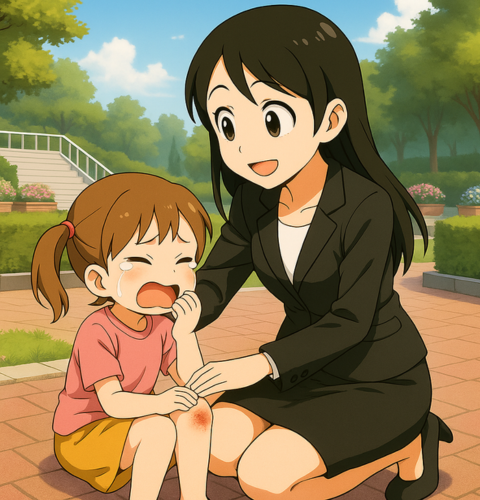

ねえねえ……ふと思ったんだけどさ、保険料ってどうやって決めてるのかな~?
この保険は亡くなる確率多そうだから保険料は高め!
この保険は支払う保険金が少ないから保険料安くしちゃおう!
そんな感じで決まってたりするの?

そんなに単純な決め方はしていないよ。
保険料は、たくさんのデータを元に“どのくらいの確率で保険金が支払われるか”を計算して、それに保険会社の運用の見込みや、運営にかかる費用を組み合わせて決めているんだ。
いわゆる3つの“予定率”というものを使って、きちんと仕組みに基づいて設定されているんだよ。

えっ、3つの予定率ってそんなに大事なの?
名前だけじゃ全然イメージつかないよ~…。
気になるからもっと詳しくきかせてよ。
どんな仕組みなのか知りたい!

おっ、きりちゃんが興味を持ってくれて何よりだよ。
3つの予定率は、保険料の仕組みを理解するうえでとても大切なんだ。
これが分かると、保険の見え方がぐっと変わってくるよ。
じゃあ今回は、“保険料はどう決まるのか”というテーマで、
3つの予定率について順番に解説していくね!
きりちゃんのように、「保険料ってどうやって決まっているの?」と素朴な疑問を抱く人は少なくありません。保険は身近な存在なのに、その仕組みとなると、どうしても専門的で分かりにくい印象がありますよね。なんとなく「この保険は高い気がする」「こっちは安く見える」など感覚で捉えてしまいがちですが、実際の保険料はそんな単純なものではありません。
保険会社は、契約者が安心して保険に加入できるよう、過去の膨大な統計データや将来の見通しをもとに、丁寧に保険料を組み立てています。事故や病気の発生率、保険金の支払いに備えるための見積もり、さらに集めた保険料をどう運用していくかといった幅広い要素を踏まえて、合理的に計算されているのです。
その計算の中心にあるのが「3つの予定率」と呼ばれる基礎となる数値です。この3つがあるおかげで、保険会社は長期間にわたって契約を守り、必要なときに保険金を支払える体制を維持しています。
今回は、この“保険料はどう決まるのか”というテーマに沿って、保険の根幹を支える3つの予定率について、分かりやすく解説していきます。

ちなみに補足なんだけど、これから解説していく“3つの予定率”は生命保険の保険料を決めるときに使われる仕組みなんだ。
医療保険や傷害保険では、入院率や事故の発生率といった別のデータを使って保険料を計算するから、そこは区別しておくと分かりやすいよ。
スキマ時間を有効活用できる【オンスク.JP】
目次
予定死亡率とは?保険料の“土台”になる数字
予定死亡率とは、**「どのくらいの確率で保険金の支払いが発生するか」**を統計データにもとづいて予測した数字のことです。
生命保険は長期にわたる契約なので、保険会社は将来に備えて、どれくらいの人が死亡する可能性があるのかをあらかじめ見積もっておく必要があります。
予定死亡率は過去の膨大な人口統計や死亡統計を分析して作られるため、
感覚や雰囲気ではなく、**科学的で客観的な根拠にもとづいた“将来の見積もり”**といえます。
この数字があることで、保険会社は
「どれくらいの保険金を将来支払うことになりそうか」
を合理的に予測し、そのために必要な保険料を計算できるようになります。

そっかあ~!
たくさんデータがあるから、“このくらいの人が亡くなるかも”って予測できて、
じゃあこれだけ保険金の準備をしておこうって考えられるんだね~。

その通りだよ。予定死亡率は、過去のデータから“どれくらいの確率で保険金の支払いが起きるか”を見積もるための数字なんだ。
この見積もりが正確なほど、保険料も適切に設定できるようになるんだ。
予定死亡率が高く見積もられるほど、
支払う保険金の可能性が高いと判断されるので、保険料は上がりやすくなります。
反対に、予定死亡率が低ければ、支払いリスクが小さいため、保険料は抑えやすくなります。
つまり予定死亡率は、
“保険料の基礎をつくる最重要データ”
といえる存在なんです。
お金で失敗する人生はもったいない「お金の教養講座」
予定利率とは?保険料を左右する“運用の見込み”
予定利率は、保険会社が「預かった保険料をどれくらい増やせるか」を見込んで設定する数字です。
ざっくり言えば、将来の運用益をどの程度期待するかという前提の値なんです。

へえ〜、預かったお金って、そのまま保管庫にしまってるだけだと思ってたよ。
運用とかって、そんなにちゃんと考えてるんだね。

そうだね。保険会社は預かったお金を適切に運用して、それを前提に保険料を計算しているんだ。
仕組みを知ると、保険料の違いにも理由があることが分かるよ。
予定利率が高いときは、
「運用で増える見込みがあるから、その分お客様から集める保険料は少なくていい」
という判断になります。
逆に予定利率が低いと、
「お金があまり増えない前提だから、必要な保険料は高くなる」
という流れになります。
つまり保険料は、
予定利率が高いほど安く、低いほど高くなる
という関係なんです。

ねえねえ、ちょっと思ったんだけどさ、予定利率って商品ごとにそんなに変わらないんじゃないの?
結局、保険会社が強めに運用するか、手堅くいくかってだけなんじゃないの?

おっ、いい質問だね。
予定利率は商品によって変わってくるんだよ。
たとえば、長い期間お金を預かれる終身保険は運用の余裕がある分、予定利率を高めに設定しやすい。
一方で、預かる期間が短い定期保険は運用できる幅が小さいから、予定利率も抑えめになりやすいんだ。

なるほど〜、そういうことなんだね。
同じ“預かるお金”でも、どれくらいの期間預かるかで運用のしやすさって変わるんだ。
聞いてみるとちゃんと理由があるんだね。すっきりしたよ!
日本最大級のまなびのマーケット
予定事業費率とは?保険運営にかかる“コストの見込み”
予定事業費率とは、保険会社がその保険商品を運営するために、将来どれくらいの費用がかかるかを見積もった割合のことです。
保険は契約したあとも、さまざまな事務作業が続きます。
・契約内容の管理
・住所変更などの事務手続き
・保険金の支払い対応
・相談窓口の運営
・システム維持
・書類処理
こうした“運営のためのコスト”をまとめて、事業費と呼びます。
予定事業費率は、この事業費がどの程度かかるかをあらかじめ計算して、保険料に反映させたものです。
予定事業費率が高くなると、その分だけ保険料も高くなり、
逆に予定事業費率が低い商品ほど、保険料を抑えやすくなります。
つまり、予定事業費率は保険料を決めるうえで欠かせない重要な要素のひとつなのです。

ちなみになんだけどさ、この保険ってコストけっこうかかるんだよね〜っていう商品ってどんなのがあるの…?

事業費がかかりやすい商品なら、変額保険が代表的だよ。
定期保険や終身保険みたいなシンプルな仕組みと比べると、特別勘定の管理や運用成績の通知が必要になる分、事務作業がどうしても増えてしまう。
保障と運用を同時に扱う仕組みだから、管理の手間も大きいんだ。
こうした事情がある商品は、予定事業費率も高めになりやすいんだよ。
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】
3つの予定率で決まる保険料のしくみを総まとめ

3つの予定率って、ちゃんと分かってくるとおもしろいね。
保険料ってこんなふうに作られてるんだ~って分かると、前よりスッと頭に入ってくる感じがするよ!

そうだね。
予定死亡率は“どれくらい支払いが起こりそうか”。
予定利率は“どの程度運用できそうか”。
予定事業費率は“どれだけコストがかかるか”。
この3つを見積もることで、保険料に無理がないよう調整しているんだ。

仕組みが分かると、保険料の差にもきちんと理由があることが分かるよね。
3つの予定率は、保険料を理解するための基本になるから、しっかり押さえておくと安心だよ!

よーし、3つの予定率ばっちり分かったよ!
これで保険の仕組みもっと楽しく読めそうだし、次に見る商品もちょっと自信もって見られそうだよ!
保険料は、
予定死亡率・予定利率・予定事業費率
という3つの数字を組み合わせて決められています。
予定死亡率は「どれくらいの確率で保険金の支払いが起こりそうか」、
予定利率は「預かったお金がどの程度運用できそうか」、
予定事業費率は「運営にどれほどのコストがかかるか」。
この3つをあらかじめ見積もることで、保険会社は無理のない保険料を設定できるようになっています。
仕組みを理解してみると、
保険料に違いがあるのにも明確な理由があることが分かります。
FP試験での学習はもちろん、実生活で保険商品を選ぶときにも役立つ知識です。
“なぜこの保険料なのか”という背景を知ることで、
これまでよりずっと納得して保険を比較できるようになります。
3つの予定率は、保険を理解するための基本となる大切なポイントです。
FP資格継続教育パック