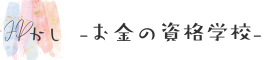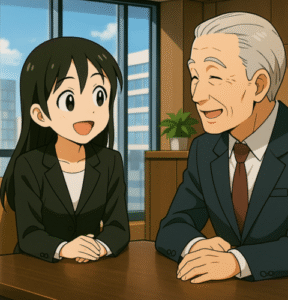FP試験にも実生活にも役立つ💡『生命保険は相続税対策として本当に有効?』
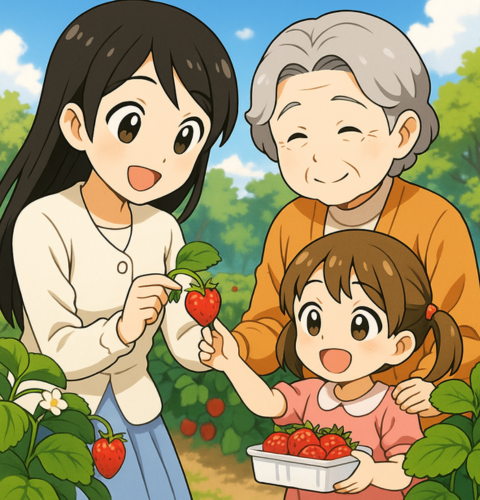

なんかね、お婆ちゃんが保険の営業さんに
『相続税対策になるから終身保険に入りましょう』って言われたらしいの。
でも本当に節税になるのかなあ…?

きりちゃん、それは家庭によってだいぶ違うよ。
まず大前提として、相続財産が基礎控除の範囲内に収まっているなら、そもそも相続税はかからない。
その場合は、終身保険に入っても“節税”という意味では効果がないんだ。
ただし、財産が基礎控除を超えている家庭なら、終身保険を使うことで非課税枠を活かせたり、納税資金を用意できたりと、役に立つこともあるよ。

えっ、基礎控除って48万円のやつだよね?
さすがにお婆ちゃん、もっと財産あると思うけどな~!

きりちゃん、それは所得税の話だよ。(きっぱり)

きりちゃん、色々と混ざってるみたいだね💦
相続税の基礎控除は『3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数』だよ。
よし、じゃあここから“生命保険は相続税対策として本当に有効なのか”をわかりやすく解説していくよ!
相続税の基礎控除は、3,000万円に法定相続人の数×600万円を加えた金額です。つまり、この範囲に相続財産が収まっている場合、相続税はそもそも発生しません。逆に財産が基礎控除を超える家庭では、相続税が生じるため、どのように納税資金を確保するかが重要になります。
ここでよく話題にあがるのが「生命保険は相続税対策として有効なのか」という点です。保険の営業担当から提案されることも多く、一見すると節税効果が高いように思えます。しかし、生命保険の活用が本当に効果的かどうかは、家族構成や財産の種類、現金の保有状況など、家庭ごとの事情によって大きく変わります。
では、生命保険は相続税対策としてどれほど有効なのか。
まずは“なぜ生命保険が相続の場面でよく使われるのか”という仕組みから、順番にわかりやすく整理していきます。
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】
目次
まずはここから!生命保険が“有効と言われる”仕組み
生命保険が相続税対策としてよく話題に上がるのは、ほかの金融商品にはない「特別な仕組み」があるからです。なかでも大きいのが、生命保険金に適用される非課税枠です。これは相続税の計算において、生命保険金の一部を相続財産に含めなくてよいという特別ルールで、金額は500万円 × 法定相続人の数と決められています。
たとえば相続人が3人いる場合、500万円×3=1,500万円が非課税となり、この部分には相続税がかかりません。銀行預金にはない優遇措置のため、生命保険は節税目的で検討されることが多いのです。

例えば保険金が3,000万円の場合、非課税枠の1,500万円を差し引いて、課税対象になるのは残りの1,500万円だけになる。
もし相続税の税率が30%なら、単純計算で450万円の節税効果が出ることになるね。

えっ、450万円も…?
そ、それは確かにかなりの節税効果だね…!
さらに、生命保険の保険金は現金で受け取れる点も大きな特徴です。相続税は原則として“現金一括納付”が求められますが、資産が不動産ばかりで現金が少ない家庭では、納税資金の準備が大きな負担となります。生命保険で受け取る保険金はそのまま納税に充てられるため、非常に実用的な対策になります。
また、生命保険には“受取人を指定できる”という性質があります。この仕組みによって、たとえば「長男には不動産、次男には保険金」というように、相続財産を分けやすくなるメリットもあります。

こういう“誰に何を遺すか”って話は、みんなが元気で落ち着いている時にこそ決めておくことが大切だよ。
いざ相続が始まってから話し合おうとすると、どうしても感情的になりやすいし、判断もぶれやすくなるからね。

うん…ほんとそうだと思う。
みんなが元気なうちにちゃんと話しておけば、お互いに気持ちが落ち着いてるから冷静に決められるし、後になって困ったり悩んだりしなくて済むもんね。
こうした非課税枠・現金性・受取人指定の三つの要素が組み合わさることで、生命保険は相続対策の場面で「有効」と言われるのです。
様々な資格学習が1078円でウケホーダイ!【オンスク.JP】
生命保険の相続対策が“向く家庭”と“向かない家庭”を整理
生命保険は相続税対策として一定の効果がありますが、どの家庭にも有効というわけではありません。節税や納税資金の確保に役立つかどうかは、家族の資産状況や財産の内訳によって大きく変わります。ここでは、生命保険を相続対策として活用しやすい家庭と、あまり向かない家庭の特徴を整理していきます。
■ 向いている家庭の特徴
● 相続税が発生しそうな資産規模の家庭
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超える財産がある場合、相続税が発生します。
このような家庭では、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)が効果的に働きます。
● 不動産が多く、現金が少ない家庭(不動産リッチ・現金プア)
不動産は評価額が大きくなりがちですが、そのままでは納税資金になりません。
生命保険金は受取時点で現金のため、納税資金の確保として非常に役立ちます。

土地を残したいのに現金が足りない、というのは相続で本当によくある話なんだ。
不動産は評価額が高くても納税には使えないし、急いで売れば安く手放すことにもなりかねない。
そんな時、生命保険の“すぐ現金が入る”という仕組みは大きな助けになるよ。納税資金さえ確保できれば、土地を無理に手放さずに済むからね。
● 財産の分け方が難しい家庭
不動産のように分けにくい財産が中心だと、相続人同士で調整が必要になります。
その際に「長男は不動産、次男は保険金」というような分割がしやすくなります。
■ 向かない家庭の特徴
● 相続財産が基礎控除内に収まる家庭
そもそも相続税がかからないため、節税効果はありません。
生命保険に加入したとしても「相続対策」としてのメリットはほぼありません。

そっかー、相続財産が3,000万円なら…
そもそも基礎控除の範囲内だから相続税って発生しないもんね。
えへへ、“節税も何も必要なかったんだ〜!”って感じだね♪
● 現金が十分にある家庭
納税資金に困らない場合、生命保険を使う意義は小さくなります。
● 保険料の負担が大きい家庭
相続対策のために保険料を払い続けると、家計を圧迫して逆効果になることがあります。

“相続税対策になるから”と安易にすすめられて保険に入って、結局たくさんの保険料を払い続けることになって、肝心の生活にまわせるお金が減ってしまったら…それは本末転倒なんだよね。
相続の備えは大切だけど、今の暮らしを苦しくしてまでやるものではない。
まずは自分たちの資産状況をしっかり見て、本当に必要かどうかを判断することが何より大事なんだよ。
このように、生命保険は“家庭の資産状況や財産の種類によっては”非常に有効ですが、誰にとっても最適な方法ではありません。自分たちの状況を整理しながら判断することが大切です。
FP資格継続教育パック
結論:生命保険は相続対策に“使える家庭・使えない家庭”がある

なるほどなんだね~!
生命保険って、みんなにとって万能な相続対策ってわけじゃないんだ~。
家庭によって“合う・合わない”があるって分かって、なんかスッキリしたよ!これ、すごく大事な気づきだねっ!

その通りだよ。相続税が発生しそうな家庭や、不動産が多くて現金が少ない家庭にはとても有効だけれど、相続税がかからない家庭や保険料が負担になる状況では、あまり意味がないんだ。
結局は状況に合わせて賢く選ぶことが大切だね。

そうだね、生命保険は相続対策として“使える家庭・使えない家庭”があるんだ。
大切なのは、自分たちの資産状況をしっかり把握した上で、本当に必要かどうかを冷静に見極めることだよ。
未来の備えと今の暮らしのバランスを忘れずにね。

よーしっ!なんだか相続のこと、前よりずっと分かってきた気がするよ~!
ちゃんと知れば怖くないんだね。これからは家族のことも、お金のことも、もっと前向きに考えていけそうだよっ!
今回の解説では、生命保険が相続税対策としてどのように役立つのか、その仕組みを「非課税枠」「納税資金」「分割のしやすさ」というポイントから振り返りました。特に重要なのは、生命保険金には 500万円 × 法定相続人の数という特別な非課税枠があることです。この枠があるおかげで、同じ現金でも保険金として受け取れば相続税の負担が軽くなる場合があります。
また、保険金は受け取るとすぐに現金として使えるため、不動産が多く現金が不足しがちな家庭では、相続発生時の納税資金として大きな助けになります。一方で、そもそも相続財産が基礎控除内に収まる家庭や、保険料が負担になる家庭の場合は、生命保険を相続対策として使う必然性は高くありません。家庭によって「向く・向かない」がはっきり分かれるのはこのためです。
大切なのは、営業トークに流されるのではなく、自分たちの資産状況やライフプランを踏まえて、本当に必要かどうかを冷静に判断することです。未来への備えと、いまの生活のゆとり、そのどちらも大切にしながら考えていく姿勢が欠かせません。
こうした考え方は、FP試験にも実生活にも役立つ知識そのものです。相続の仕組みを理解しておけば、必要以上に不安になることもなく、自分たちにとって最適な選択ができるようになります。
お金で失敗する人生はもったいない「お金の教養講座」