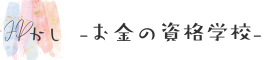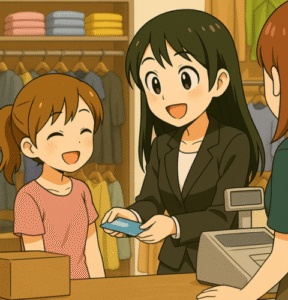FP試験にも実生活にも役立つ💡『もし銀行が倒産したら?預金保険制度の仕組み』

ねえ、なんでみんな当たり前のように銀行にお金を預けてるの?
銀行だって“絶対に倒産しない”なんて言いきれないじゃん!
あーもう💦こうしちゃいられない!
全部引き出してタンス預金にしなきゃ!

きりちゃん、あんたまた極端な子ね……。
でも大丈夫。銀行が倒産しても“預金保険制度”があるんだ。
1つの金融機関ごとに元本1,000万円とその利息まではちゃんと守られる。
だから慌てて引き出す必要はないのさ。

えっ、1,000万円も守られるの!?
それなら安心だね~。
そんな制度があるなんて知らなかったよ。
知ってるだけで、気持ちの余裕が全然ちがうね~!

そうだね、きりちゃん。たしかに、自分のお金が本当に守られるのかって不安になるよね。
でも大丈夫。ちゃんと備えられる仕組みがあるんだ。
じゃあ今回は、その“預金保険制度の仕組み”について、わかりやすく解説していこうか。
預けているお金が本当に守られるのか、不安に思うのは自然なことです。
ニュースなどで銀行の経営問題を耳にすると、
「もし自分の預金がなくなったら…」と心配になる人も少なくありません。
でも実際には、私たちの預金を守るための“預金保険制度”という仕組みが整えられています。
これは、万が一金融機関が破たんしたときに、
預金者のお金を一定の範囲内で保護するための制度です。
それでは、もし銀行が倒産したらどうなるのか——
このあと、預金保険制度の仕組みについてくわしく見ていきましょう。
目次
もし銀行が倒産したら?預金保険制度の仕組みをやさしく解説!
預金保険制度は、銀行などの金融機関が経営破たんした場合に、
預金者の大切なお金を一定の範囲で守るための仕組みです。
この制度を運営しているのは「預金保険機構(DICJ)」。
政府、日本銀行、そして民間の金融機関の出資によって設立され、
公的な立場から預金者を保護する役割を担っています。

へぇ〜、政府に日銀に金融機関まで出資してくれてるなんて、
なんだかすごく頼もしい制度だね!
いろんなところが協力して、みんなのお金を守ってくれてるんだ〜。
また、国内の金融機関はすべてこの制度への加入が義務づけられているため、
私たちが普段利用している銀行は、必ずこの保護の対象になっています。
そして安心なのは、預金者が特別な手続きをする必要はないという点です。
もし万が一、銀行が倒産しても、自動的に預金保険の対象として保護が受けられる仕組みになっています。

“預金保険制度”は自動的に適用される仕組みだからね。
『えっ、そんな手続きした覚えないんだけど!?』って焦らなくても大丈夫。
預けているだけで、ちゃんと保護の対象になってるんだ。
預金保険制度の対象となる金融機関とは?
預金保険制度の対象となるのは、国内で預金業務を行っている金融機関です。
具体的には、次のようなところが含まれます。
- 銀行(都市銀行・地方銀行)
- 信用金庫・信用組合
- 労働金庫
- ゆうちょ銀行
これらの金融機関は、すべて預金保険制度への加入が義務づけられています。
つまり、私たちが普段使っている多くの銀行が、この制度によって保護されているということです。

じゃあ私が預けてる地銀も対象なんだね!
よかった〜、ちゃんと守られてるってわかると安心するね。
ただし、注意が必要なのは、保護の対象となる銀行であっても海外の支店は対象外という点です。
日本国内での預金だけが保護の対象となるため、海外支店に預けたお金はこの制度の範囲外になります。
また、外国銀行の在日支店など、一部の金融機関は制度の対象外です。
ただし、そうした機関でも独自の保護制度を設けている場合があるため、利用前に確認しておくと安心です。

え〜、海外の銀行でも日本に支店があるなら、
保護の対象になってもいい気がするけどな〜?

まあ、そういうことになるね。
海外の銀行は日本の制度の対象外だから、“日本の預金保険制度に入らなきゃいけない”って義務もないんだ。
本店がある国の法律や制度に従ってるから、日本のルールだけではカバーできないんだよ。
| 対象金融機関 | 対象とならない金融機関 |
|---|---|
|
|
どんな預金が守られるの?預金保険制度の対象をチェック!
預金保険制度は、金融機関が破たんしてしまった場合に、
預金者のお金を一定の範囲で保護する仕組みです。
ただし、すべての預金が守られるわけではなく、
対象となる預金とそうでない預金が明確に区分されています。
| 保護の対象となる預金 | 保護の対象外となる預金 |
|---|---|
|
|

えっ、外貨預金って対象外だったの!?💦
最近、利回りがいいからちょっと預けてみようかな~って思ってたのに……。
そっか、保護してもらえないなら慎重に考えないとだね。
うーん、やっぱり何事もメリットだけってわけにはいかないか〜。

いいところに気づいたね、きりちゃん。
外貨預金は魅力的だけど、リスクもきちんと見て判断できるのはとても大事なことだよ。
お金の世界では“増やす力”だけじゃなく、“守る力”も同じくらい価値があるんだ。
外貨預金は、為替の動きによって円預金よりも高い利回りが期待できるなど、
魅力的な一面を持つ商品です。
しかしその一方で、預金保険制度の対象外であることから、
万が一金融機関が破たんした場合には、預けたお金が保護されないというリスクもあります。
また、為替相場の変動によっては、円に戻した際に元本割れする可能性もあります。
つまり、外貨預金は「増えるチャンスがある」代わりに「減る可能性もある」商品なのです。
だからこそ、きりちゃんのように「利回りだけでなく、リスクもしっかり考える」姿勢はとても大切です。
お金を増やす力と同じくらい、お金を守る力を持つことが、
これからの資産づくりにおいて欠かせない考え方といえます。
どこまで守られる?預金保険制度の保護範囲をチェック!
預金保険制度では、金融機関が経営破たんした場合に、
預金者の資産を「どのくらいの範囲で」保護するのかがあらかじめ決められています。
その保護範囲は、**「全額保護される預金」と「1,000万円まで保護される預金」**の2つに分かれます。
全額保護の対象となる「決済用預金」
「決済用預金」とは、次の3つの条件をすべて満たす預金のことです。
- 利息がつかない(無利息)
- いつでも払い戻しができる(要求払い)
- 決済に使える(振込などに利用できる)
代表的なものが当座預金です。
このような決済用預金は、社会の決済機能を守るため、
元本全額が保護の対象となっています。

むむっ、利息がつかないのか〜!
全額保護って聞いてちょっと惹かれたけど、
やっぱりここでも“メリットばっかり”ってわけにはいかないんだね〜。

うん、そう感じるのもわかるよ。
たしかに“全額保護”って聞くと安心だけど、利息がつかないのはちょっと惜しいよね。
でも、それは“安全性を最優先にした預金”だからなんだ。
金融機関としても、全額守る分だけ利息をつけないことでバランスを取ってるんだよ。
一般の預金(普通・定期など)の場合
普通預金や定期預金などの一般預金は、
**1つの金融機関ごとに「元本1,000万円とその利息まで」**が保護されます。
たとえば、A銀行に1,200万円預けていた場合、
1,000万円とその利息までは預金保険制度によって保護されますが、
残りの200万円は金融機関の財産状況に応じて支払われる仕組みです。
このように、預金の種類によって保護の範囲が異なります。
全額保護か、1,000万円までなのかを知っておくことで、
安心して預金を管理できるようになります

そっか〜、私はまだ1,000万円も貯金できてないけど、
もし到達したら別で新しく口座をつくるのもアリだね〜。
ちょっとした工夫でリスクを減らせるって、なんか賢い感じするな〜!

よく考えてるね、さすがきりちゃん!
ひとつだけ気をつけておくといいのは、同じ銀行の別支店に口座をつくっても、
預金保険では“同じ金融機関”として扱われるってこと。
もし1,000万円を超えるようになったら、別の銀行に分けて預けるようにすると安心だよ。
預金保険制度のポイントをまとめておさらい!

いや〜、最初は“銀行が倒産したらどうしよう!”って不安だったけど、
ちゃんと預金保険制度で守られてるってわかって安心したよ〜。

そうだね。
国内の金融機関ならほとんどが加入してるし、
普通預金や定期預金は1,000万円とその利息まで保護される。
決済用預金は全額保護だから、安心感がちがうね。

うん、ふたりともよく理解できてるね。
大事なのは、“どこに”、“どの種類の預金を”預けているかを意識すること。
支店を分けても同じ銀行なら1,000万円の枠は変わらないし、
外貨預金や投資商品は保護の対象外だから注意しておこう。
こうして制度の仕組みを知っておくことが、
自分のお金をしっかり守る力につながるんだよ。

なるほど〜!ちゃんと仕組みを知っておけば、いざって時も落ち着いて行動できるね。
お金のことって難しそうだけど、こうやって理解していけば怖くないかも!
よ〜し、これからは“守る力”も育てていくぞ〜!
預金保険制度は、金融機関が破たんした場合に預金者の資産を守るための大切な仕組みです。
国内の金融機関は原則としてすべてこの制度に加入しており、
普通預金や定期預金などの一般預金は、1つの金融機関ごとに「元本1,000万円とその利息まで」保護されます。
一方で、決済用預金(当座預金など)は全額保護の対象となるなど、
預金の種類によって保護範囲が異なります。
また、外貨預金や投資信託といった金融商品は保護対象外なので注意が必要です。
同じ銀行の別支店に口座を分けても、預金保険上は「同じ金融機関」として扱われるため、
1,000万円の上限は合算されます。
複数の銀行に分けて預けることで、万が一の際のリスクを抑えることができます。
預金保険制度の仕組みを正しく理解しておくことは、
自分の資産を“増やす”だけでなく“守る”ための第一歩です。
安心してお金を預けるためにも、ぜひこの制度を覚えておきましょう。