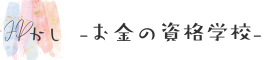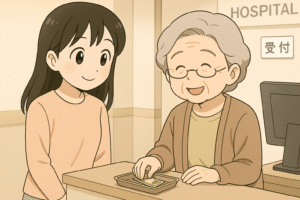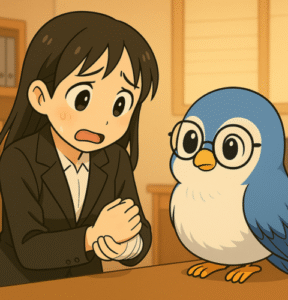老後の“生活”を守る仕組み、公的介護保険をわかりやすく解説
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】
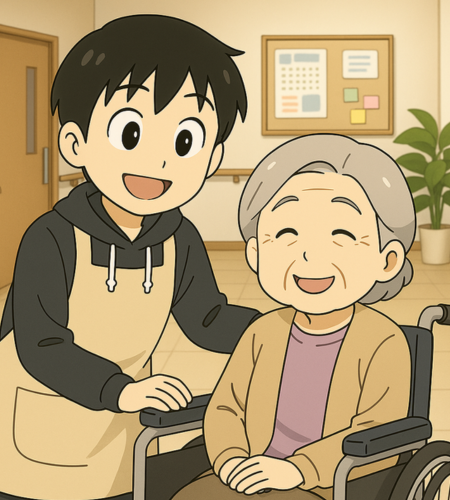

日本の医療保険がすごく充実してるのは分かったんだけど、
介護の方ってどうなってるの?

介護保険もかなり充実してるよ。
高齢になると医療と同じくらい、介護サービスを使う人が増えてくるからね。

たしかに、車いすが必要だったり、認知症になったりしたら、一人じゃ生活むずかしいよね。
でも私、介護保険料なんて払ってないんだけど…?
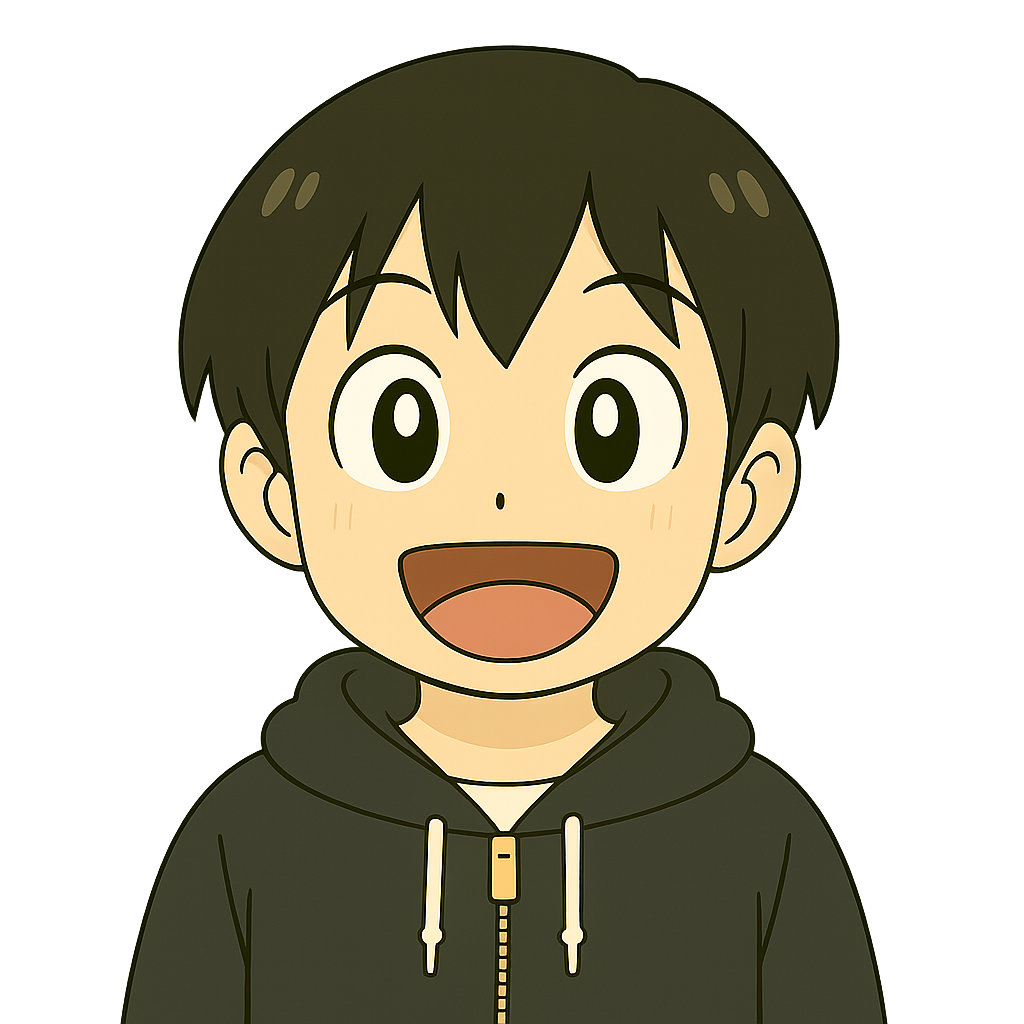
それは当然だよ。介護保険料の支払いは40歳からだからね。
よし、それじゃあ今回は《公的介護保険》について、わかりやすく解説していくよ!
医療と並んで、老後の生活を支える大事な制度だから正しく理解しよう!
年齢を重ねると、手足が思うように動かなくなり、食事や入浴、排せつなど、日常生活の動作が難しくなってきます。
そんなとき、生活を支えてくれるのが「介護」の存在です。
これからの日本はますます高齢化が進み、介護の必要性はどんどん高まっていきます。
だからこそ、介護の土台を支える「公的介護保険制度」について、今のうちから正しく学んでおくことが大切です。
公的介護保険の対象は?加入する年齢としくみ
介護が必要になったときに支えてくれる「公的介護保険制度」は、40歳になると加入する仕組みになっています。

40歳になったらもう加入しないといけないの?
介護が必要な人なんてまだほとんどいなくない…?

たしかに40代はまだ介護なんて遠い話に感じるよね。
でもね、65歳から保険料を払い始めても、支えるお金がぜんぜん足りないんだ。
だから40歳から少しずつ“支える側”として準備しておくってわけなんだ
まず、加入者は2つのグループに分けられます。
ひとつ目は65歳以上の人(=第1号被保険者)。
この人たちは、介護が必要と認定されれば、原因を問わず介護サービスを利用できます。
もうひとつは40歳以上65歳未満の人(=第2号被保険者)。
このグループは、がんや認知症など、加齢に関係する「特定の病気」が原因で介護が必要になった場合に限り、サービスを使えるしくみです。
そして、この制度を運営しているのが、私たちが住んでいる市区町村(保険者)です。
介護が必要になったときに、申請を受けたり、認定をしたり、保険料を管理したりと、重要な役割を担っています。
| 区分 | 対象年齢 | サービス利用の条件 | 主な対象原因 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 要支援・要介護と認定されればOK(原因は問わない) | 骨折、認知症、老衰 など |
| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 要支援・要介護と認定+ 特定疾病が原因であること |
初老期認知症、脳血管疾患、がん末期 など |

第2号被保険者のサービス利用条件きびしいね。

うん、たしかに第2号は“特定の病気”じゃないとサービス受けられないから、ちょっと厳しく感じるよね。
この制度は高齢になったときに本格的に使う前提で作られてるから、
40歳から65歳になるまでは“将来への準備期間”って考えるといいかも。
公的介護保険料について
✅ 40歳~64歳の人(第2号被保険者)
この世代は、公的医療保険に加入していれば、介護保険料の支払い義務があります。
つまり、会社員などの健康保険加入者だけでなく、自営業・無職などで国民健康保険(国保)に加入している人も対象です。
- 会社員など → 健康保険料に上乗せされて、給与から天引き(会社と折半)
- 国保の人 → 国民健康保険料と一緒に、市区町村から世帯単位で請求される
ただし、この世代はまだ「現役世代」として位置づけられており、
介護保険のサービスを利用するには、認知症や脳血管疾患など“加齢に関係する特定の病気”が原因で要介護認定を受けた場合に限られます。

月のお給料が40万円の人は保険料いくらくらいなのかな…?

月40万円の人だと、自己負担分は約3,500円くらいかな。そこまで大きな金額ではないね。

自分の場合はいくらぐらいだろう?って知りたい人は『協会けんぽや各組合のホームページ』から確認できるよ。
月額表の見方はこちらの記事からチェックしてみてね。
✅ 65歳以上の人(第1号被保険者)
保険料は、住んでいる市区町村が決めた金額を、年金から天引き(特別徴収)されるのが基本です。
年金が少ない人などは、口座振替で払うケースもあります。
保険料の金額は、本人の所得に応じて段階的に決められていて、所得が高い人は多めに、低所得の人には軽減措置がある仕組みです。

65歳以上で会社員の人も給与からの天引きじゃなくて年金からの天引きになるの…?

年金をもらっていれば、介護保険料は原則“年金から天引き”されるんだよ。
もし年金が年間18万円未満だったり、まだ年金を受け取ってなかったりすると、
給与からの天引きじゃなくて、自分で支払う“普通徴収”になることもあるんだ。
介護認定と費用負担

介護保険で受けられるサービスは、日常生活を支えるためのサポートが中心です。
「要支援」または「要介護」の認定を受けると、その状態に応じて必要なサービスを利用することができます。
| 区分 | 内容の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | ほぼ自立しているが軽度の支援が必要 |
| 要支援2 | 立ち上がりや移動に不安があり継続的な支援が必要 |
| 要介護1 | 部分的に介助が必要な状態 |
| 要介護2 | 日常生活での支援がさらに必要な状態 |
| 要介護3 | 排せつ・食事などにも介助が必要 |
| 要介護4 | ほとんどの動作に全面的な介助が必要 |
| 要介護5 | 寝たきりや重度認知症など、常時介助が必要 |

介護度が上がると保障の面でどんな良いことがあるの…?

介護度が上がると、使えるサービスの量が増えて、保険でカバーされる金額も多くなるんだよ。
だから、必要な支援をちゃんと受けやすくなるんだ。
介護保険で受けられるサービスは、
「人に来てもらう(訪問)」「施設に通う(通所)」「施設に入る(入所)」の大きく3つに分かれています。
それぞれの生活スタイルや介護の重さに合わせて、
食事・入浴・排せつなど、日常生活の手助けを受けることができます。
そのほかにも、福祉用具のレンタルや自宅のバリアフリー改修の補助なども含まれています。
✅費用負担は?
介護保険サービスを利用するときは、原則1割負担(※所得によって2割・3割になる人も)。
残りは介護保険財源から給付されます。
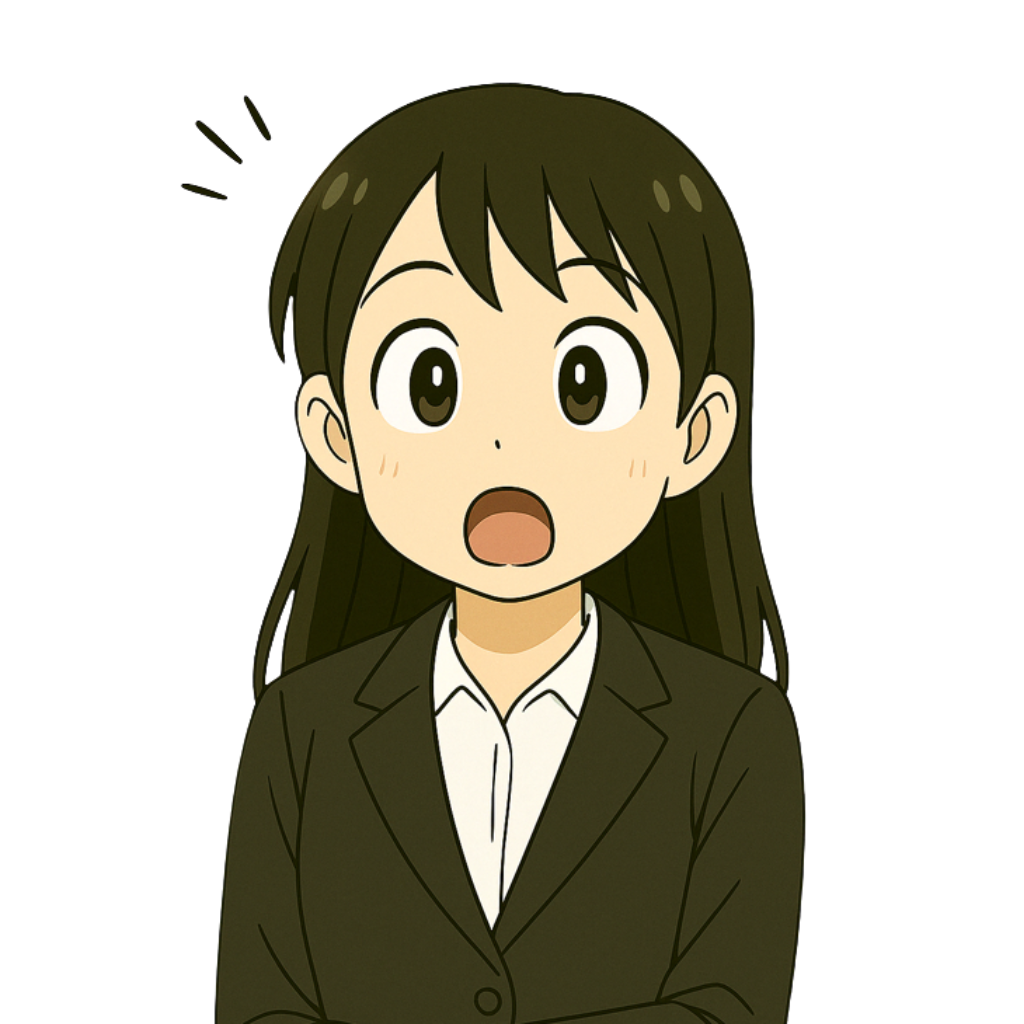
おお!1割でいいんだ!
なんか所得によって2割・3割って部分も含めて後期医療と似てるね…!

きりちゃん大正解っ!✨
どっちも75歳以上の後期高齢者が多く利用する制度だから、よく似てる部分が多いんだよ。
じつは両方とも“みんなで支え合う”って考え方がベースになってるんだ。
まとめ:介護保険と“現役世代”の公平性
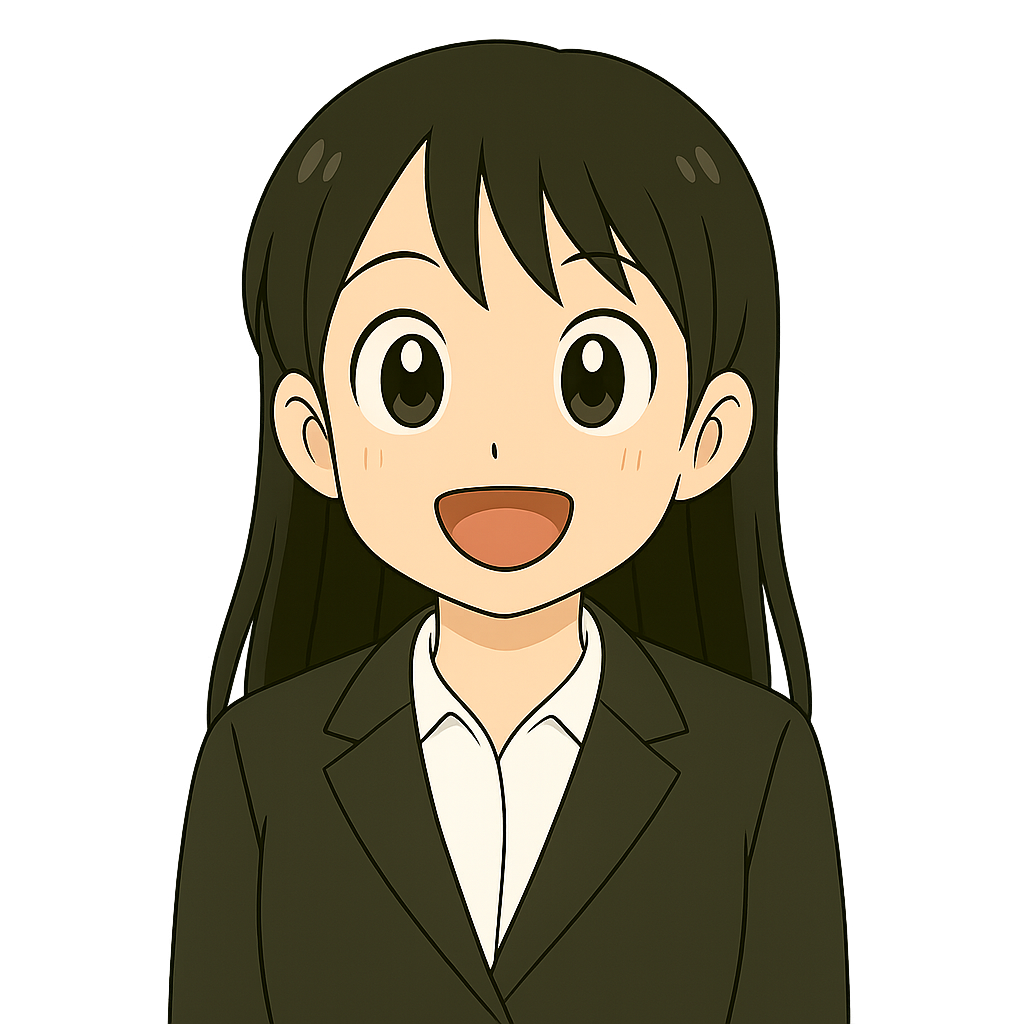
介護保険って思ってたよりもしっかりしてるんだね!
特に介護認定が7段階も分かれてるなんてビックリしたよ!

それぞれの人に必要なサービスを“ムダなく”届けるために、
あえて段階を細かく分けてるんだ。
その人の状態に合わせて、使えるサービスの量や内容が変わるから、
“必要な分だけ、ちゃんと支える”っていうしくみなんだよ。

もし身近な人が介護認定を受けたときに、
“どんなサービスが使えるか”とか“自己負担はいくらか”ってパッと答えられたら、
それだけで信頼されるかっこいいFPになれるよ!

よ~しっ!誰かが困ってもすぐに教えてあげられる、
かっこいい“介護もわかるFP”になるぞ~!🔥✨
公的介護保険は、介護度に応じて「要支援1・2」から「要介護1~5」までの7段階に分かれており、
それぞれの状態に合わせて利用できるサービスや給付の上限額が細かく設計されています。
この仕組みによって、介護が必要な人それぞれに適切な支援を届ける“公平性”が保たれているという良い面があります。
ただ個人的には、この細かさが制度をやや複雑にしていると感じており、
健康保険や後期高齢者医療制度と比べても、とっつきにくさを覚える保険制度でもあります。
また、医療保険と同様に、介護の現場も高齢者人口の増加に伴って人手不足が深刻化しています。
特に入所施設では、日勤・早番・夜勤の不規則なシフト勤務が一般的で、
さらに入浴や排せつの介助など、想像以上に体力を要する肉体労働であることに加え、
認知症の利用者によっては暴言・暴力・不穏行動などへの対応も必要になるなど、
精神面でも負担の大きい仕事です。
それにもかかわらず、給与水準は決して高いとは言えず、
仕事の重さに見合わない待遇が離職の原因にもなっています。
介護度による細かな区分は、利用者間の公平性を保つためには大切な仕組みですが、
その制度を支えている現役世代の負担の公平性にも、もっと目を向ける必要があると感じます。
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】