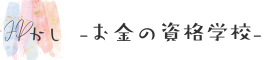後期高齢者医療制度の対象者・保険料・給付内容とは?
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】
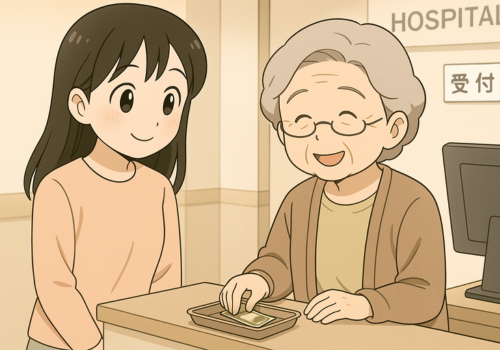

そういえば、健康保険も国民健康保険も“75歳未満”って対象だったけど、、、
えっ!?75歳になったら保険に入れないの!?日本のこと…見損なったよ!!

ちょっとちょっと、落ち着いて💦
75歳になったら、“後期高齢者医療制度”っていう別の保険に自動で切り替わるんだよ。

しかもねこの制度、自己負担が軽くなるから実質的には負担が少なくて済むんだよ。

なーんだ!そういうことなら安心だよ~♪
さすが長寿大国・ニッポンっ!!✨

…手のひら返しすごいな。
日本では、75歳になると、それまで加入していた健康保険(協会けんぽや組合けんぽ)、国民健康保険などに関係なく、全員が自動的に「後期高齢者医療制度」へ切り替わります。
この制度では、他の医療保険制度と比べて自己負担の割合や医療費の上限が抑えられているため、高齢者にとってはとても利用しやすい仕組みになっています。
さらに、こうした高齢者専用の医療制度が整備されている国は世界的にもめずらしく、この制度こそが日本が“長寿大国”でいられる大きな支えとなっています。
目次
後期高齢者医療制度とは?
日本では、75歳になると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険などから自動的に「後期高齢者医療制度」へ切り替わることになります。これは全国共通のルールで、特別な申請や手続きは基本的に不要です。

後期高齢者医療制度、略して“後期医療”ってみんな呼んでるね。
加入できる人(加入条件)
以下のいずれかに該当する人は、後期高齢者医療制度に加入することになります:
- 75歳以上のすべての人
- 65歳以上74歳未満で一定の障害があると認定された人(申請が必要)
👉 つまり、原則として75歳以上になれば全員が対象です。

『勝手に切り替えないでよー!』とはならないの…?

あまりいないね。保険料も軽いし、医療費も減るし、手続きも勝手にやってくれるし…
むしろ『切り替え大歓迎!』って人の方が多いと思うな。

ただし、一見すると本人にはメリットが多い制度に見えるけど、
それまで“家族の扶養に入っていた人”や、逆に“家族を扶養に入れていた人”にとっては、
保険料の負担が新たに発生することで、むしろ“損した”と感じる場面もあるんだよ。
後期高齢者医療制度の保険料について
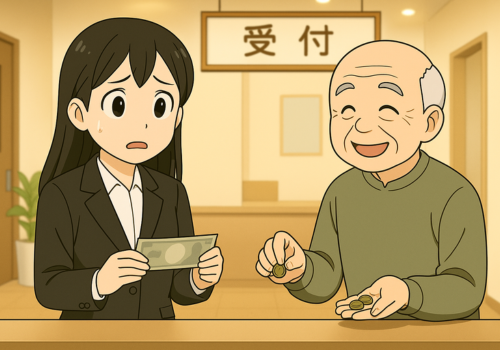
後期高齢者医療制度の保険料は、原則として各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」が徴収を行います。
これは、市区町村ではなく、都道府県単位で運営されている仕組みで、全国一律ではなく地域ごとに保険料の金額や計算方法が異なるのが特徴です。
保険料の差はどのくらい?
2025年度の後期高齢者医療制度の保険料(月額)👇
| 都道府県 | 月額保険料(※年金収入のみの一般的なケース) |
|---|---|
| 福岡県(最も高い) | 約6,641円 |
| 岩手県(最も安い) | 約4,808円 |
| 全国平均 | 約5,673円 |
【出典:厚生労働省(後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について)】
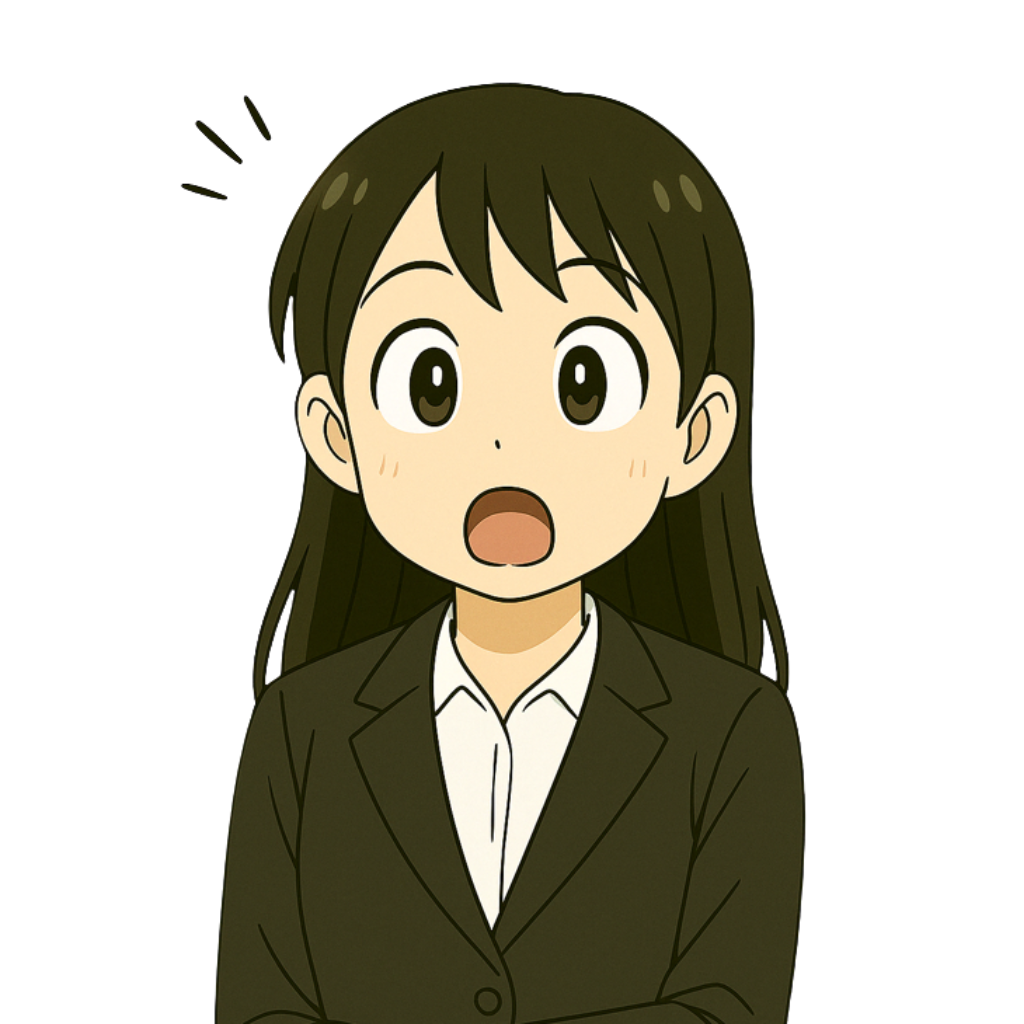
ひゃ~、住む場所によって保険料ってけっこう違うんだね。
年間で数万円の差があるよ…!

たしかに県ごとで保険料に差はあるけど、
それでも健保や国保と比べたら、後期医療の保険料ってかなり安いね。
保険料は、加入者それぞれの所得や年金の金額などに応じて個人ごとに決定されます。
そして、実際の支払い方法としては、ほとんどの人が年金からの天引き(特別徴収)で納めています。
そのため、毎月自分で納付する必要はなく、「気づいたらちゃんと払えてる」仕組みになっているんです。
ただし、年金額が一定未満の場合などは、口座振替や納付書での支払い(普通徴収)になるケースもあります。
給付内容:療養の給付
後期高齢者医療制度では、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合が軽く抑えられているのが特徴です。
- 所得が一定以下の人は、原則として自己負担1割
- 所得の多い人については、自己負担割合が2割または3割に引き上げられることもある
これは、高齢者が経済的な不安なく医療を受けられるようにするための配慮です。一方で、負担の公平性を保つために、所得の高い人にはそれなりの負担も求める仕組みになっています。
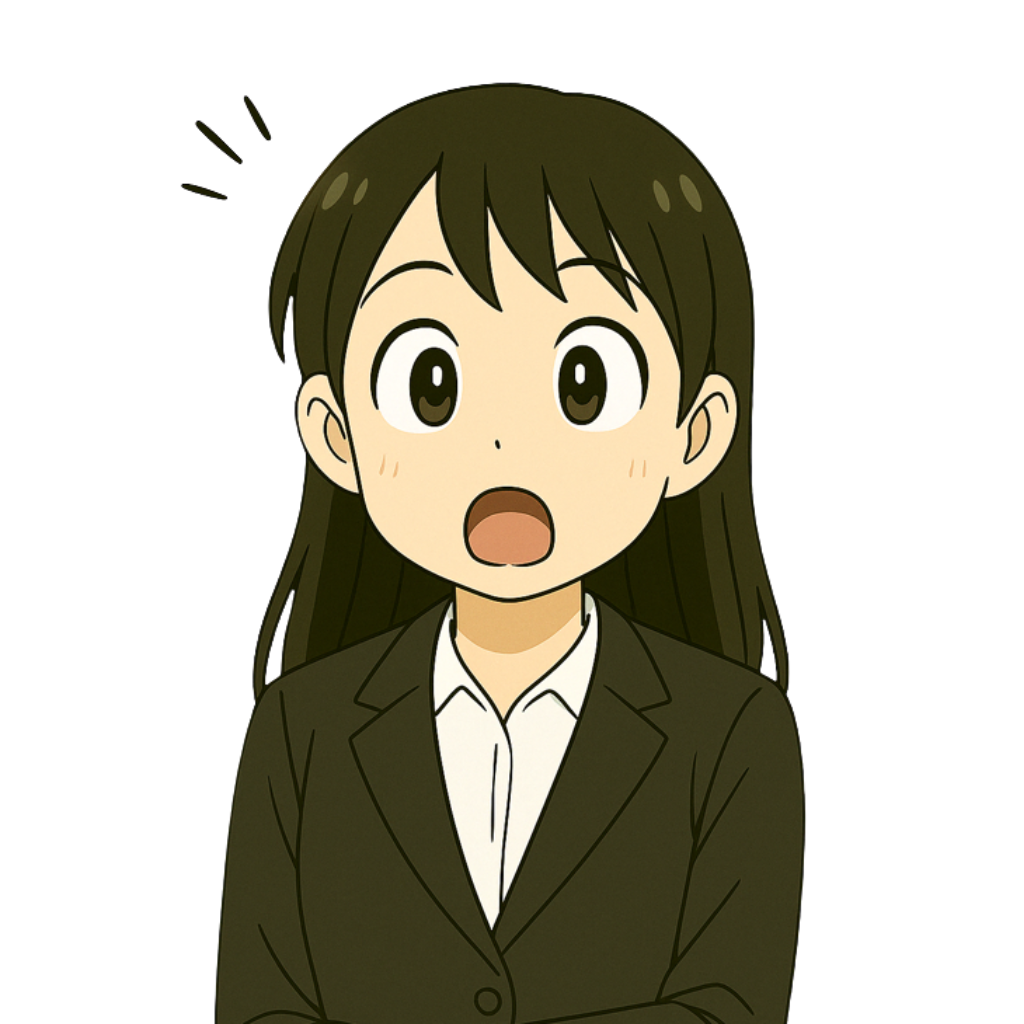
えっ、医療費って1割でいいの…?
ということは、医療費が1万だとしたら…1,000円!?っやす。

うん、年金暮らしの人とか、所得が低い人は基本1割だよ。
でもね、現役並みに働いてしっかり稼いでる人は、2割とか3割になることもあるよ。

国としては、『ちゃんと稼いでるなら、1割負担じゃなくてもいいでしょ?』って考えなんだと思うよ。
給付内容:高額療養費制度
高額療養費制度とは、1か月の医療費の自己負担額が一定の上限(自己負担限度額)を超えた場合、その超過分を後から払い戻してくれる制度です。
たとえば入院や大きな手術などで自己負担が高額になっても、この制度があるから家計が守られる!という仕組み。

健保や国保の高額療養費と何が違うの?

上限額が圧倒的に少ないね。
表でまとめてみたよ。
| 保険の種類 | 所得の目安 | 通常の上限額 | 多数回該当時の上限額 |
|---|---|---|---|
| 健保・国保(一般) | 年収 約370万〜770万円 | 57,600円 | 44,400円 |
| 後期高齢者医療制度(一般) | 課税所得145万円未満程度 | 18,000円 | 15,000円 |
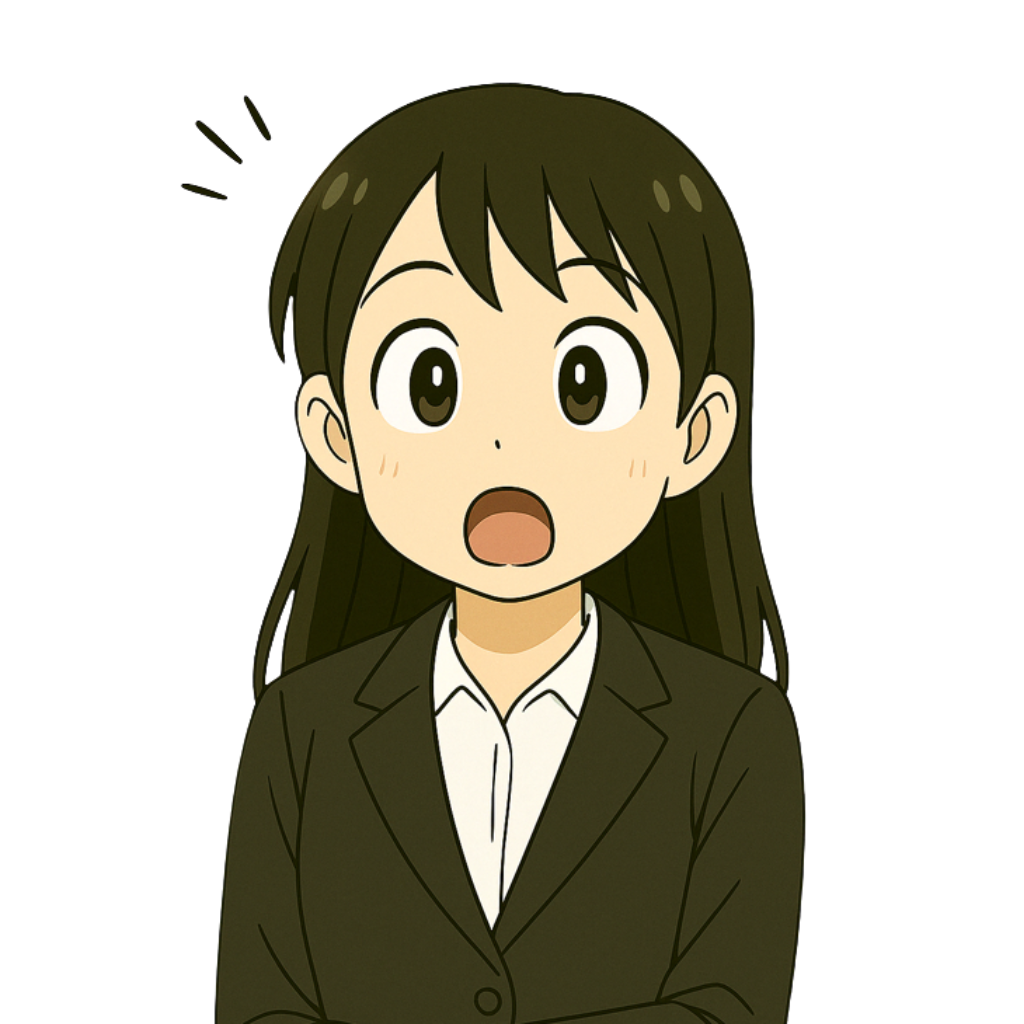
すご!2万円未満で済んでる…!

他の所得の場合で確認したい方はこちら(東京都後期高齢者医療広域連合)で確認してね。
また現役世代時の高額療養費と同様に、同じ人が過去12か月で3回以上、上限に達した場合、4回目からは“さらに低い上限”が適用される仕組みです。
これも、高齢者に優しいポイントの一つですね。
まとめ:高齢者にやさしい制度、でも将来はどうなる?

ふふっ、よかった!これで安心して老後を迎えられるね♪
おじいちゃんもおばあちゃんも、ずっと元気でいてほしいな。

ほんと、医療費の不安が減るってすごく大きいことだよね。
でも、その安心をどう守り続けるかがこれからのカギかも。

そうそう、制度を支える現役世代の負担は増えているのも事実だよ。
“やさしい制度”を、ちゃんと“続けられる制度”にしていくのが今後の日本の課題だね。
日本の公的医療保険制度──たとえば健康保険や国民健康保険などは、世界的に見ても非常に優れた仕組みです。
誰もが平等に医療を受けられ、自己負担も抑えられているこの制度は、誇るべき社会インフラのひとつだと言えるでしょう。
そんな中でも、後期高齢者医療制度は、それらをさらに上回る“超優秀な制度”です。
高齢者の方々が安心して医療を受けられるよう、1割から最大でも3割という低い自己負担で整備されており、まさに手厚い制度だと思います。
ただ、正直に言えば、個人的にはオーバースペックなのではないかと感じる部分もあります。
というのも、いまの日本は「少子高齢化」や「人口減少」といった構造的な課題を抱えており、
“人生100年時代”という言葉が現実味を帯びる中、今後も医療・介護の需要は増え続けていくのは確実です。
当然、その財源を支える現役世代の負担は年々重くなり、そのツケは未来を担う子どもたちが払っていくことになります。
たとえ改悪につながる改正があっても、感情的な批判ではなく、
「これは改悪ではなく、必要な見直しなんだ」
「将来の日本や子どもたちのために必要なことなんだ」
──そう思ってくれる方々が、少しでも増えてほしいと願っています。
そしてそのために、これからも、正確な情報をわかりやすく、丁寧に発信し続けていきます。
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】