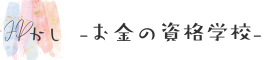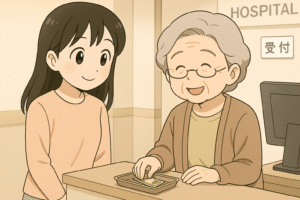国民健康保険とは?仕組み・保険料・加入条件をわかりやすく解説
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】

私は会社員だから“健康保険”に入ってるけど、退職して無職になったら、どこに加入すればいいのかな?

その場合は、“国民健康保険”に入ることになるよ。次の転職先が決まるまではね。

健康保険と国民健康保険って名前が似てて、ややこしいね~。

“健康保険”はよく“健保(けんぽ)”って略されて、
“国民健康保険”は“国保(こくほ)”って呼ばれるんだ。
略称で呼ぶと少しスッキリして、区別もしやすくなるよ。
じゃあ今回は、自営業者や無職の人が主に入る“国保”について、解説していくよ!
目次
健康保険と国民健康保険、名前がややこしい
健康保険と国民健康保険。
名前がそっくりで「何が違うの?」と感じたことがある人も多いのではないでしょうか?
これらは「歴史的な流れ」と「制度の広がり方」に理由があります。
- 先にあったのが「健康保険(健保)」
→ 明治・大正のころから始まった、会社員向けの保険制度です。
→ 正式名称は「健康保険法に基づく健康保険」、だから“健康保険”ってストレートな名前になりました。 - あとから生まれたのが「国民健康保険(国保)」
→ 農家・自営業・無職の人にも保障が必要だ!ってことで昭和にできた制度
→ 「全国民が入れる健康保険」って意味で“国民”ってつけたけど、
結果的に名前がそっくりになってしまいました。 - 両方「健康保険」って言っちゃうと…
→ 日常会話でも混ざるし、制度を説明する側もややこしい!
→ だから略称で「健保(けんぽ)」「国保(こくほ)」って分けて使うようになっています。

へー、“国民健康保険”って後から生まれたんだ。

そうそう。“国民みんなが入れる保険”っていう象徴として、この名前にしたんだよ。
かつての日本では、すべての人が医療保険に入れるわけではありませんでした。
健康保険は主に会社員向けの制度として整備されていたため、自営業者や農家、無職の人などは医療費を全額自己負担することが多かったのです。
こうした中で、誰もが安心して医療を受けられる社会を目指して整備されたのが「国民健康保険」です。
1961年(昭和36年)、国民健康保険の全国展開が完了し、すべての国民が何らかの医療保険に加入できる体制が整いました。
これにより、日本は「国民皆保険」を実現。誰もが医療費の自己負担を抑え、必要な医療を受けられる仕組みが全国に行き渡ったのです。
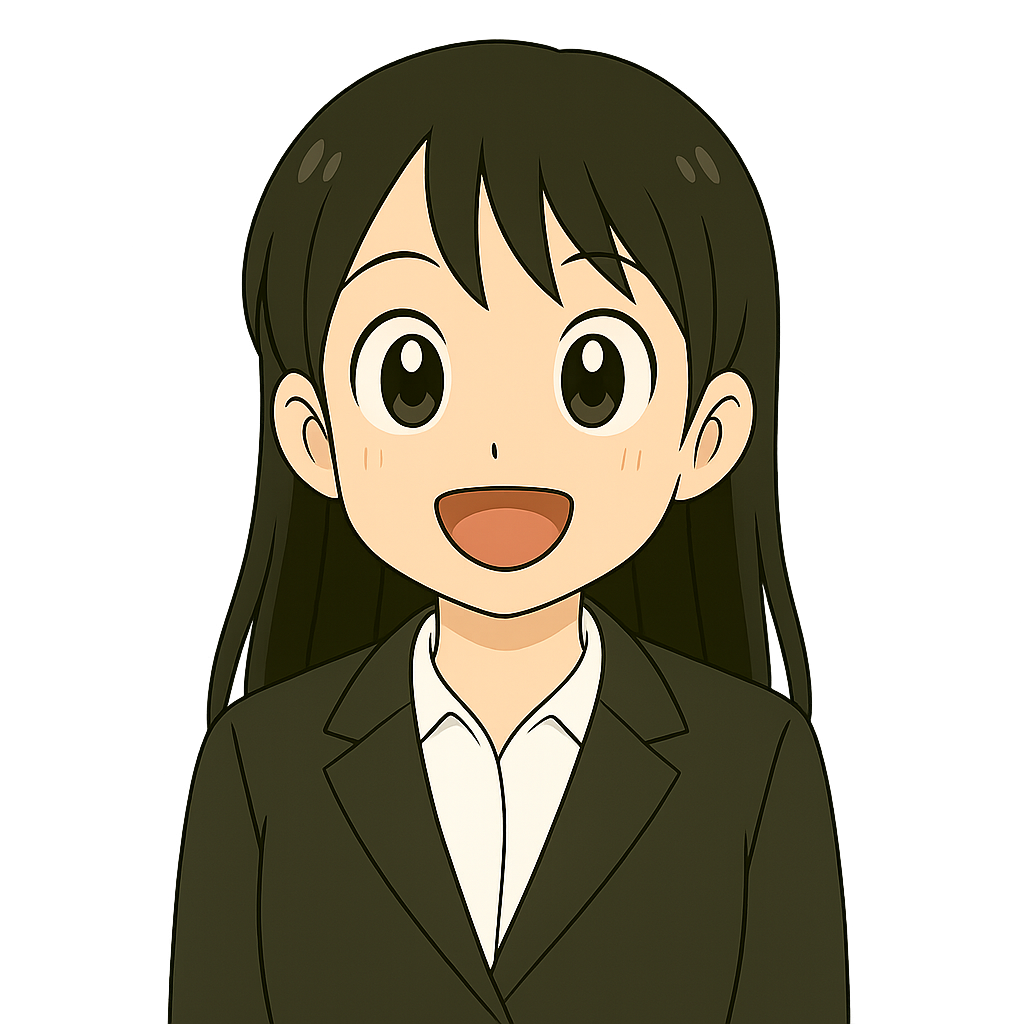
そうだったんだ…!
こうした歴史を知ると『国民全員が保険に入れてるのって当り前じゃないんだ!』って感じるよ。

そうだね。昔は入れない人もいっぱいいたんだよ。
だからこそ今の仕組みって、実はすごくありがたいことなんだよね。
国民健康保険に加入するのはどんな人?
国民健康保険(国保)は、会社の健康保険に入れない人のための公的な医療保険制度です。
そのため、加入するのは主に以下のような人たちです。
- 自営業者やフリーランスの人
- 農業や漁業に従事している人
- 退職して無職の人
- アルバイトやパートなどで勤務先の健康保険に入れない人
- 上記の人に扶養されている配偶者や子どもなどの家族

会社員や公務員とその扶養家族(75歳未満)以外の人が、国保に入るって考えればOK!
国民健康保険の保険料はどう決まる?
国民健康保険の保険料は、会社の健康保険のように「給料の◯%」といった形では決まりません。
市区町村ごとに計算方法や金額が異なり、住んでいる地域によって負担額に差があります。
保険料は大きく分けて、以下のような要素で構成されています。
- 所得割
→ 前年の所得に応じて決まる部分です。所得が多いほど保険料も高くなります。 - 均等割
→ 世帯内の加入者1人につき一定額がかかります。人数が多いとその分増えます。 - 平等割(世帯割)
→ 世帯ごとに一律でかかる額です。 - 資産割(導入している自治体のみ)
→ 固定資産税の額をもとに算出されることがあります。
こうした仕組みによって、同じ年収でも住んでいる場所や家族構成によって保険料が大きく変わるのが国保の特徴です。
また、保険料の納付は原則として世帯主がまとめて支払うことになります。

国保には“扶養”の仕組みがないから配偶者や子どもが多いほど、その人数分しっかり保険料がかかっちゃうんだ。
協会けんぽ(健保)と国民健康保険(国保)保険料シミュレーション
月収40万円・扶養あり(配偶者+子ども1人)の場合の
協会けんぽ(健保)と国民健康保険(国保)の年間・月額保険料の比較です👇
| 項目 | 年間保険料(概算) | 月額換算(概算) |
|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ) | 246,000円 | 20,500円 |
| 国民健康保険(東京都23区) | 510,010円 | 42,501円 |

ひゃ~!毎月の保険料が倍以上違う!
こりゃ自営業で養っていくのはかなり大変そうだね💦

ちなみにたとえ独身でも、国保は全額自己負担だから健保より保険料は高くなりやすいんだ。
収入がある程度あると、その差がけっこう大きくなるんだよね。
国民健康保険と健康保険の給付内容比較

比較的健康保険より国民健康保険の方が保険料が高いっていうことは、保障が手厚かったりする…?

うーん、実は“保険料が高い=保障が手厚い”ってわけじゃないんだ。
国保は全額自己負担だし、傷病手当金や出産手当金もないから、保障の中身は健保の方がずっと手厚いんだよ。
| 給付内容 | 国民健康保険(国保) | 健康保険(健保) |
|---|---|---|
| 医療費の自己負担 | 原則3割 | 原則3割 |
| 高額療養費制度 | あり | あり |
| 出産育児一時金 | あり(原則50万円) | あり(原則50万円) |
| 傷病手当金 | なし | あり(最長1年半、給与の約2/3) |
| 出産手当金 | なし | あり(産前産後に給与の約2/3) |
| 埋葬料・埋葬費 | あり(原則5万円) | あり(原則5万円、または家族は5万円) |
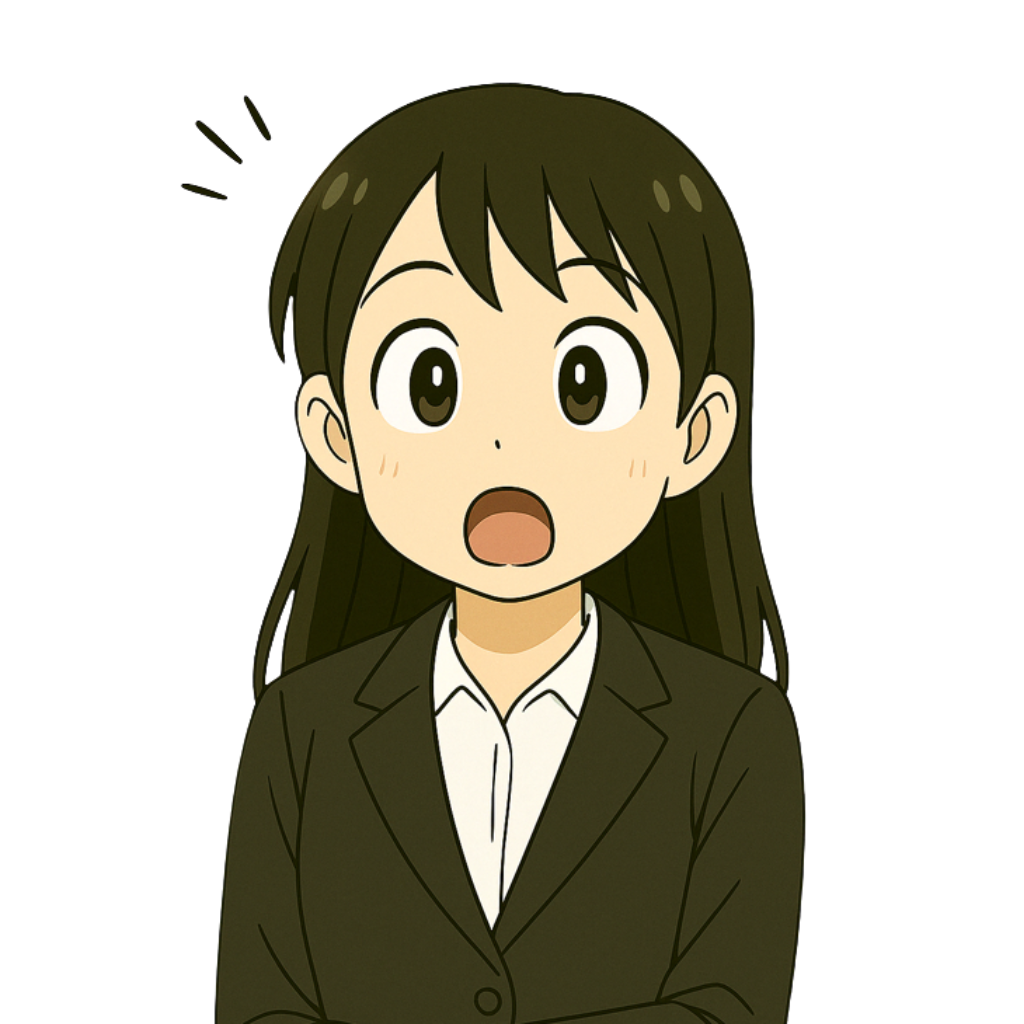
はえ~、傷病手当金と出産手当金の保障がないし、
『ここは健保より国保の方が手厚い』っていうのも一切ないんだね…。
国民健康保険は、会社員などが加入する健康保険と比べると、どうしても保障面で見劣りしてしまう部分があります。
たとえば、国保には傷病手当金や出産手当金がないため、病気や出産で働けなくなったときの生活保障がありません。
さらに、保険料についても国保の方が高くなるケースが多く、家計への負担は大きくなりがちです。
一方、健康保険は会社が保険料を半分負担してくれるため、個人の負担は軽く、加えて保障内容も手厚くなっています。
この「会社の支え」があるかどうかが、保険料と保障の大きな差につながっているのです。
とはいえ、国保も基本的な医療保障はしっかり整っています。
医療費の自己負担は原則3割ですし、医療費が高額になった場合は高額療養費制度によって限度額を超えた分が払い戻されます。
国内では健保と比較されてやや不利に見える国保ですが、世界的に見ると日本の国民健康保険制度は非常に高水準であり、
「誰もが医療を受けられる仕組み」として高く評価されています。

“国民皆保険”当り前じゃないからね。
まとめ:国民健康保険って損なの?実はすごい日本の医療制度

うーん、会社辞めた後に入る“国保”って、保険料高いのに保障は少ないってちょっとショックかも、、、

たしかに健保と比べると『えっ、国保高すぎ!』って感じるよね。
でも“保険料を会社が半分出してくれる”って、健保がすごすぎるんだよ。

そうそう。でも国保も悪い制度ってわけじゃないよ。
医療費は3割負担だし、高額療養費制度もあるし、世界的に見ればかなりしっかりした仕組みなんだ。
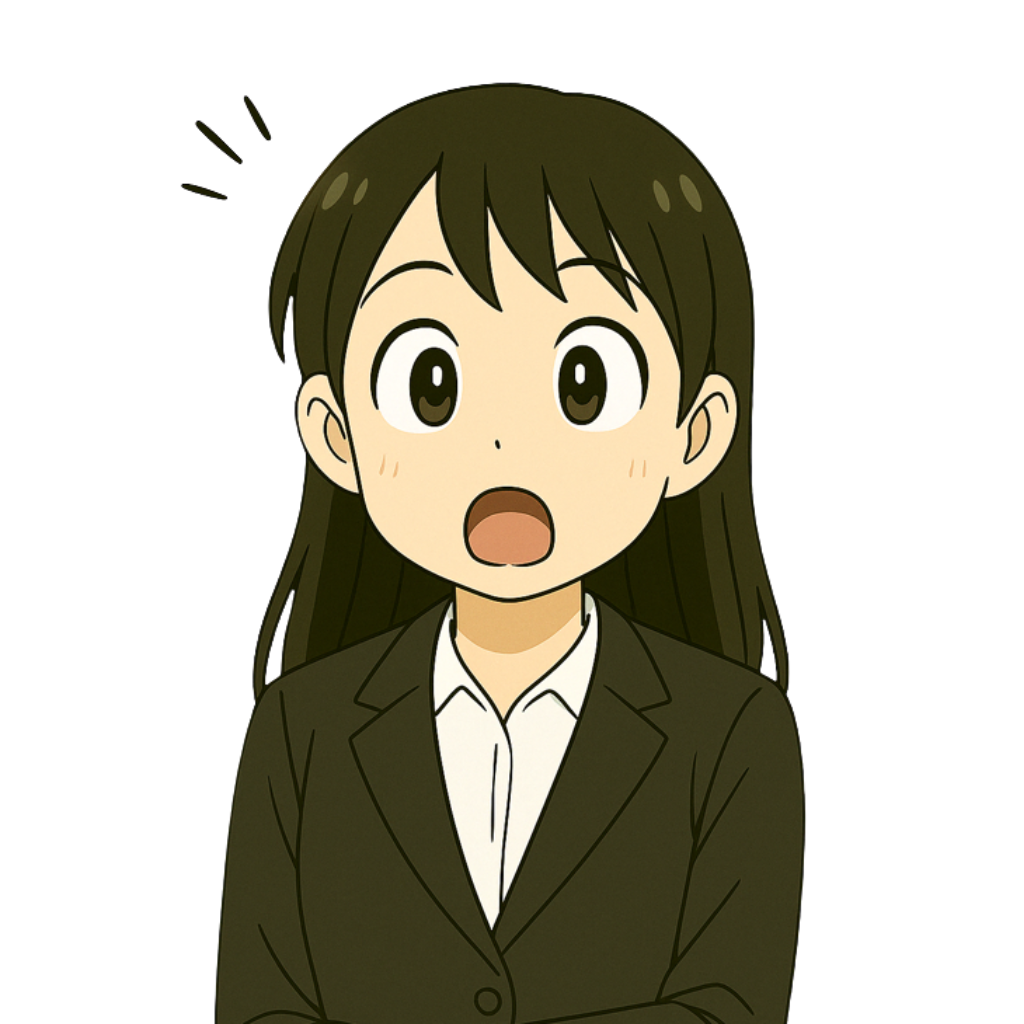
えっ!?これって当たり前じゃないの?他の国って違うの?

全然違うよ。アメリカなんて保険に入ってなくて医療費が払えない人もたくさんいるんだ。
日本は“保険に入ってれば安心して病院に行ける”って、実はすごいことなんだよ。

たとえ保障がシンプルでも、“国民皆保険”って制度がちゃんと守られてる国って意外と少ないんだよ。
だから国保は世界トップクラスの素晴らしい保険なんだ!
最後に:FPかしの独り言
今回は「国民健康保険」について解説してきました!
正直なところ、会社員として健康保険に加入している立場から見ると、国民健康保険はどうしても見劣りしてしまう部分があります。
とくに、傷病手当金や出産手当金がないことを知ると、今の健保との違いに思わず比較してしまう人も多いはずです。
それでも、医療費の自己負担が原則3割で済むことや、高額療養費制度で一定額を超えた分は払い戻されるといった仕組みを知ると、
「本当に良い時代と良い国に生まれたなあ」と、しみじみ感じます。
SNSなどでは、増税や社会保障制度の変更があるたびに批判の声が目立ちますが、
私はまず「今ある制度のありがたさに感謝する気持ち」を大切にしたいと思っています。
もちろん、これからの日本は人口減少・少子高齢化が進み、社会保障の“改悪”は避けられないでしょう。
だからこそ、未来に備えた資産管理や体調管理がますます重要になります。
『保険料払ってばっかで病院全然行ってないよー』って言えるくらい、健康寿命を延ばしていきたいですね。(笑)
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】