保険制度の基本はここから!2大原則を学ぼう
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】

きりちゃん、10人の村って保険制度は成り立つと思う?

えっ、なんか唐突💦
別に成り立つんじゃないの?人数って関係あるー?

これがね、人数って超重要!
1,000人規模の村じゃないと成り立たないんじゃないかな。
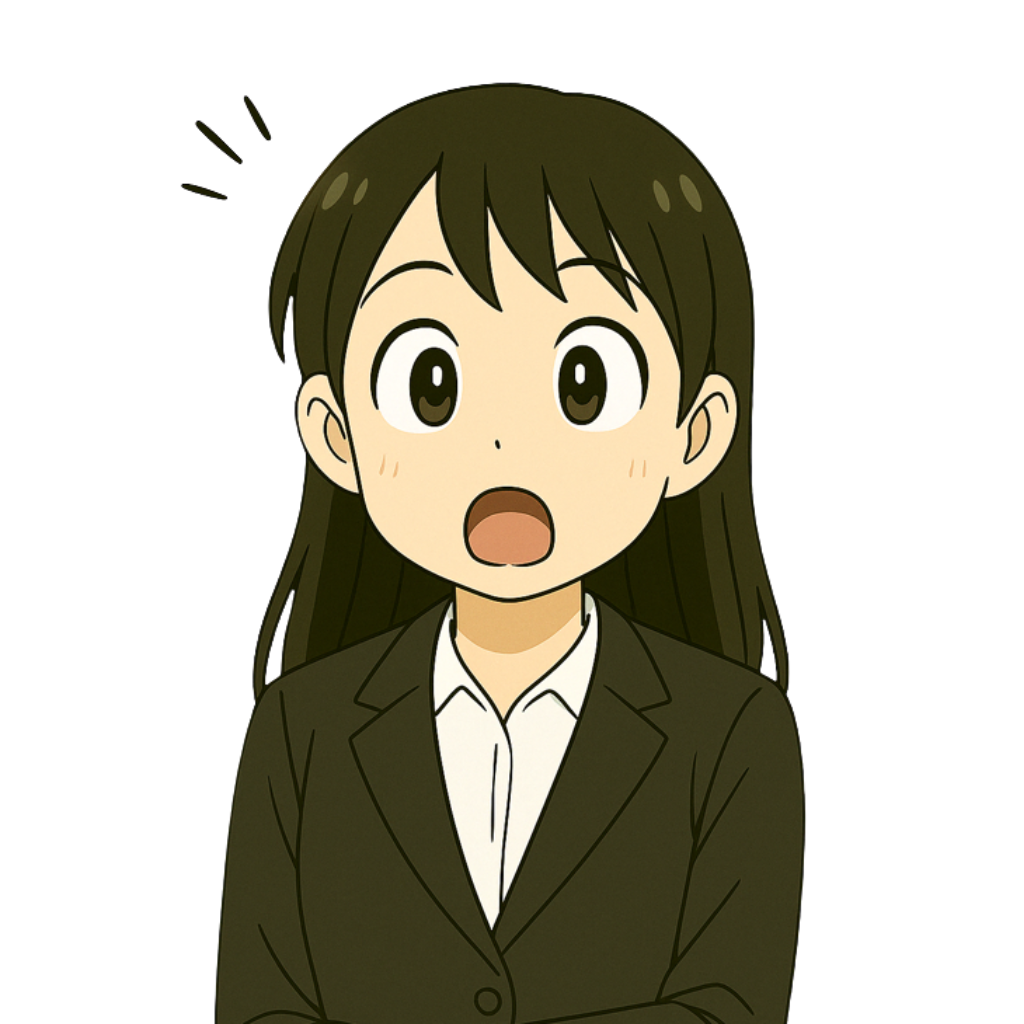
えっ、そんなに!?なんでなんでー?

OK!じゃあ今回は保険制度を成り立たせる2つの原則について解説していくよ!
目次
保険の原則①:大数の法則
「大数の法則」は、保険制度の土台を支える統計的な考え方です。
カンタンに言うと、
たくさんの人が集まれば、将来のリスク(病気・けがなど)の発生率は“だいたい予測どおり”に落ち着く
という法則です。

人数が多いとほど発生率が “だいたい予測” どおりって本当なの?

本当だよ!サイコロで例えるね。
サイコロで1の目が出る確率を調べてみた!
サイコロの「1の目」が出る確率は、理論的には **1/6(16.7%)**です。
これを10回と1,000回で実際に振ってみて、出た目の回数と確率を比べてみました!
✅ シミュレーション結果
| 試行回数 | 1の出た回数 | 出現確率(1の目) |
|---|---|---|
| 10回 | 2回 | 20% |
| 1,000回 | 169回 | 16.9% |
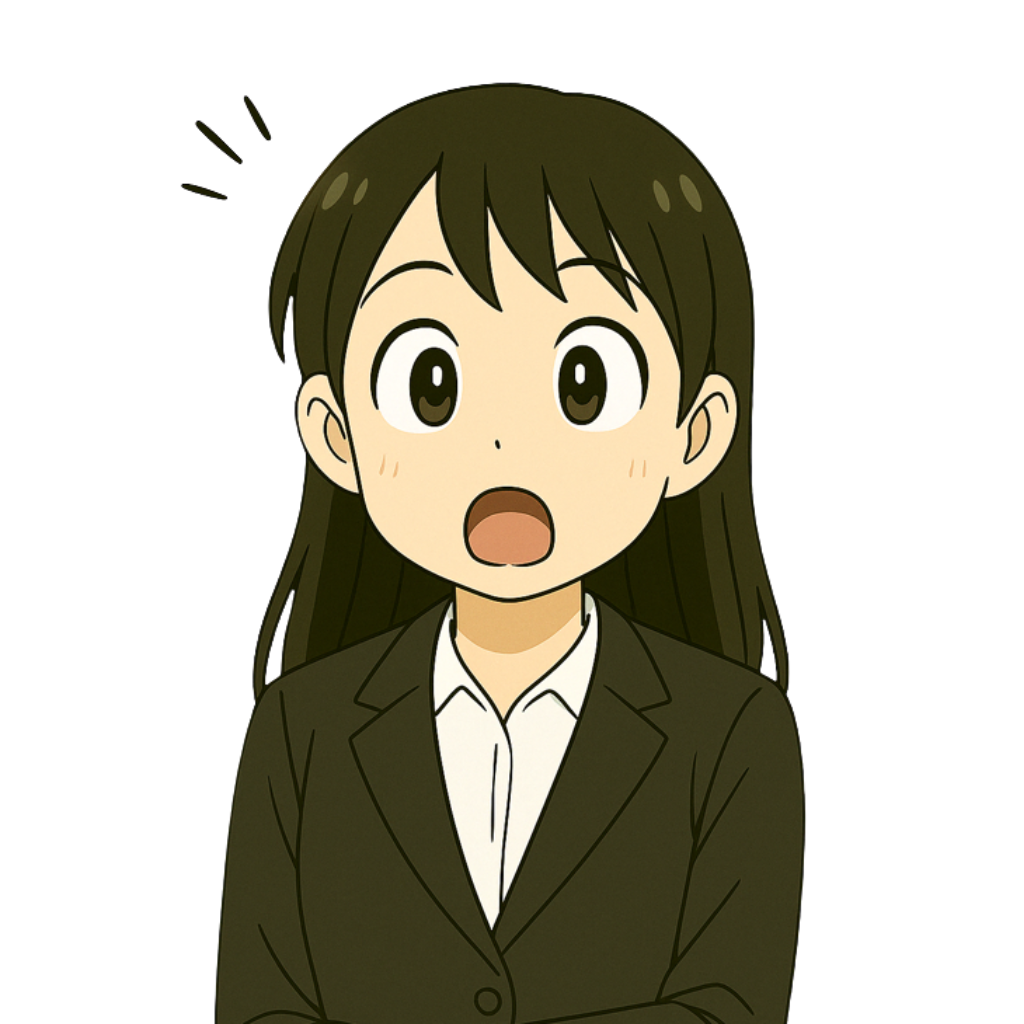
おお!1,000回サイコロ振った方が理論値(16.7%)に近い!

でしょ?このように、回数が増えるほど“本来の確率”に近づくのが大数の法則の特徴なんだよ!
これが保険制度とどう関係あるの?
保険は「未来に何が起こるかはわからないけど、 “だいたいこんな割合で起きるだろう” 」はある程度予測できます。
この「だいたい」がわかる仕組みこそが、大数の法則!
たとえばこんなイメージ:
- がんになる確率が100人に1人(=1%)だとわかっていれば、1,000人いれば約10人ががんになると予測できる。
- つまり、どれくらいの人数が集まれば、どれくらいの支出が発生するかを見積もれる。
- 予測ができれば、そこから逆算して「1人あたりどれくらい保険料を集めればいいか」の計算ができる。
つまり、、、
大数の法則によって「見積もり」ができるようになるからこそ、制度そのものが“設計可能”になる。
「10人しかいなければ、リスクが“平均化”されない=誰も病気にならなければ黒字、1人でも大病すれば大赤字」
つまり、制度として“安定しない”=制度として成り立たたなくなります。

なるほどね〜。
人数が多くないと保険制度が成り立たない理由って、
『見積額を予測するため』だったんだね。

そうだね。たとえば、誰も病気にならなかった年は『保険料はゼロでOK!』ってなるけど、
翌年に誰かが大病して1,000万円かかったら、『じゃあ10人で割って、1人100万円ずつ負担してね』って話になるんだ。
そうなると、毎年の保険料がバラバラで安定しないし、最初からいくら集めればいいかの見積もりも立てられないんだよね。
保険の原則②:収支相等の原則
収支相等の原則(しゅうしそうとうのげんそく)とは、
収入と支出の均衡を保つことを目的とした仕組みです。
つまり、“入ってくるお金”と“出ていくお金”をつり合わせよう!という、保険制度を成り立たせるための大切なルールです!

ふ~ん、でもなんで『収入』と『支出』を均衡にしないとダメなの…?

たとえばね、集めた保険料よりも給付の方が多くなっちゃうと、制度は赤字になって続かなくなるんだ。
かといって、保険料をすっごく多めに取りすぎると、今度は『なんでそんなに払わなくちゃいけないんだ!』って人が抜けちゃうかもしれないよね。

だからちょうどいいところ——つまり、『必要な分だけを、必要な人から、無理なく集める』。
そのバランスを取るために、『収入と支出を均衡にする』っていう考え方が大事なんだよ!
保険制度を支える「収支相等の原則」
保険会社は、支出に対して過剰な収入(保険料)を集めてはいけません。
保険は、あくまで「みんなで支え合う」ことを目的とした制度だからです。
とはいえ、保険会社はボランティア団体ではありません。
営利企業として事業を継続する以上、支出が収入を上回るような赤字経営では、ビジネスとして成り立ちません。
だからこそ大切なのが、「収支相等の原則」です。
つまり、支出に見合った収入(保険料)を確保しつつ、適正な利益も含めて、全体のバランスを取ること。
このバランスが保たれているからこそ、私たちは安心して保険に加入できるのです。
保険は、ただの“お金のやり取り”ではなく、「みんなで支え合う」制度として設計されているのです。
公的・民間・共済の違いから見る“保険のバランス感覚”
収支相等の原則にもっとも忠実なのが「都道府県民共済」です。
非営利の団体として運営されているため、利益を目的にしておらず、もし保険料を多く集めすぎた場合は、その分を「割戻金」という形で加入者に返す仕組みになっています。
一方で、民間の保険会社は営利企業であるため、保険料収入の中には事業運営費や予定利益も含まれており、支出よりも収入の方が高くなる傾向があります。
また、公的保険は制度設計上は収支相等の原則に基づいていますが、現実には少子高齢化の影響を強く受けており、給付(支出)の方が多くなっています。その不足分は税金などの公費で補われているのが現状です。
だからこそ、保険に加入する際は「この保険料は、実際に戻ってくる保障と比べて高すぎないか?」という視点を持つことがとても大切です。
保険は安心を買うものですが、その中身をしっかり見極める力も、これからの時代には欠かせません。
| 区分 | 運営主体 | 目的 | 収支の特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 公的保険 | 国・自治体等 | 社会保障 | 給付 > 収入(不足分は税金で補填) | 少子高齢化でバランスが崩れ気味 |
| 民間保険 | 営利企業 | 収益確保+保障 | 収入 > 支出(予定利潤+経費含む) | 利益を前提とした保険料設計 |
| 都道府県民共済 | 非営利団体 | 助け合い(共済) | 収入 ≒ 支出(余剰分は割戻金として返還) | 非営利で、加入者に還元される仕組み |
まとめ:大数の法則と収支相等の原則から見る保険の本質

保険って人数が多くないと成り立たないし、収入と支出のバランスも大事だったんだねー。
思ってた以上に奥が深い制度だ…!

うんうん、まさに“人数の力”と“数字のバランス”で動いてる制度なんだよ。
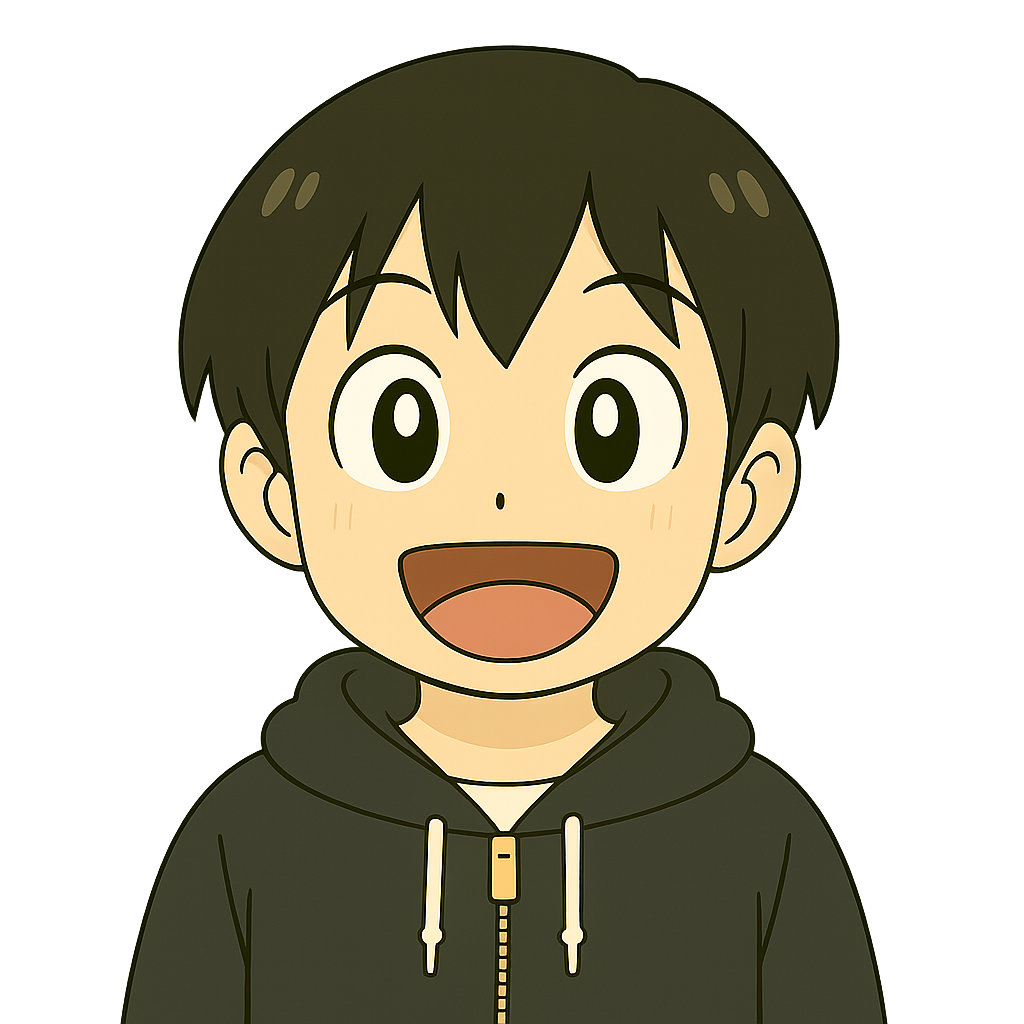
この2つの原則をちゃんと知っておけば、
マイナーな保険を紹介されたときに『加入者が少なすぎたら、大数の法則が働かなくて制度自体が不安定なんじゃない?』って気づけるようになるし、
SNSやテレビで派手に広告してる保険を見たときも『こんなに広告費かけてるってことは、そのぶん保険料も高くなるんじゃない?』って考えられるようになるよ。
そうやって、おかしな保険を見極められる力がついてくるんだ!

なるほど〜!保険を選ぶときって、ただ安いとか有名だからじゃなくて、ちゃんと“しくみ”を見ることが大事なんだね!✨
最後に:FPかしの独り言
今回は、保険制度を支える2つの原則「大数の法則」と「収支相等の原則」について解説しました!
この記事を書きながら、改めて少子高齢化が保険制度に与える影響の大きさを実感しました。
公的保険制度では、収入の基盤となる現役世代の人数が年々減っている一方で、給付の中心となる高齢世代の人数は増え続けています。
そのような状況で収支相等の原則を維持しようとすれば、保険料の負担はどうしても増加していかざるを得ません。
そこで現在は、税金という新たな収入源を加えることで、制度のバランスを何とか保っているのが現実です。
さらに、人口減少も保険制度にとって深刻な問題です。
大数の法則の観点から見ると、加入者が減ることで「どれくらいのお金が必要になるか」の見込みがズレやすくなり、
その結果、保険料が安定しなかったり、高くなってしまったりする原因になるんです。
少子高齢化と人口減少のダブルパンチによって、保険制度の運営は今後ますます難しくなっていくと考えられます。
だからこそ、私たち自身が「保険に頼りすぎなくても大丈夫な状態」を目指して、
日ごろから貯蓄を増やしたり、収入を増やす力をつけたりと、自己防衛力を高めておくことがとても重要になってくるのです。
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】
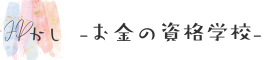
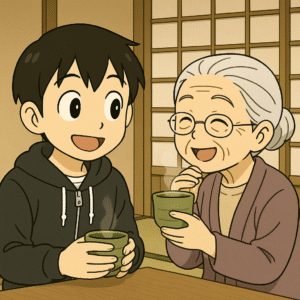

“保険制度の基本はここから!2大原則を学ぼう” に対して1件のコメントがあります。