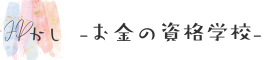ファイナンシャル・プランナー(FP)はどこまでできる?意外と知らない業務の境界線
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】
FPが踏み込んではいけない「士業の専門領域」って?
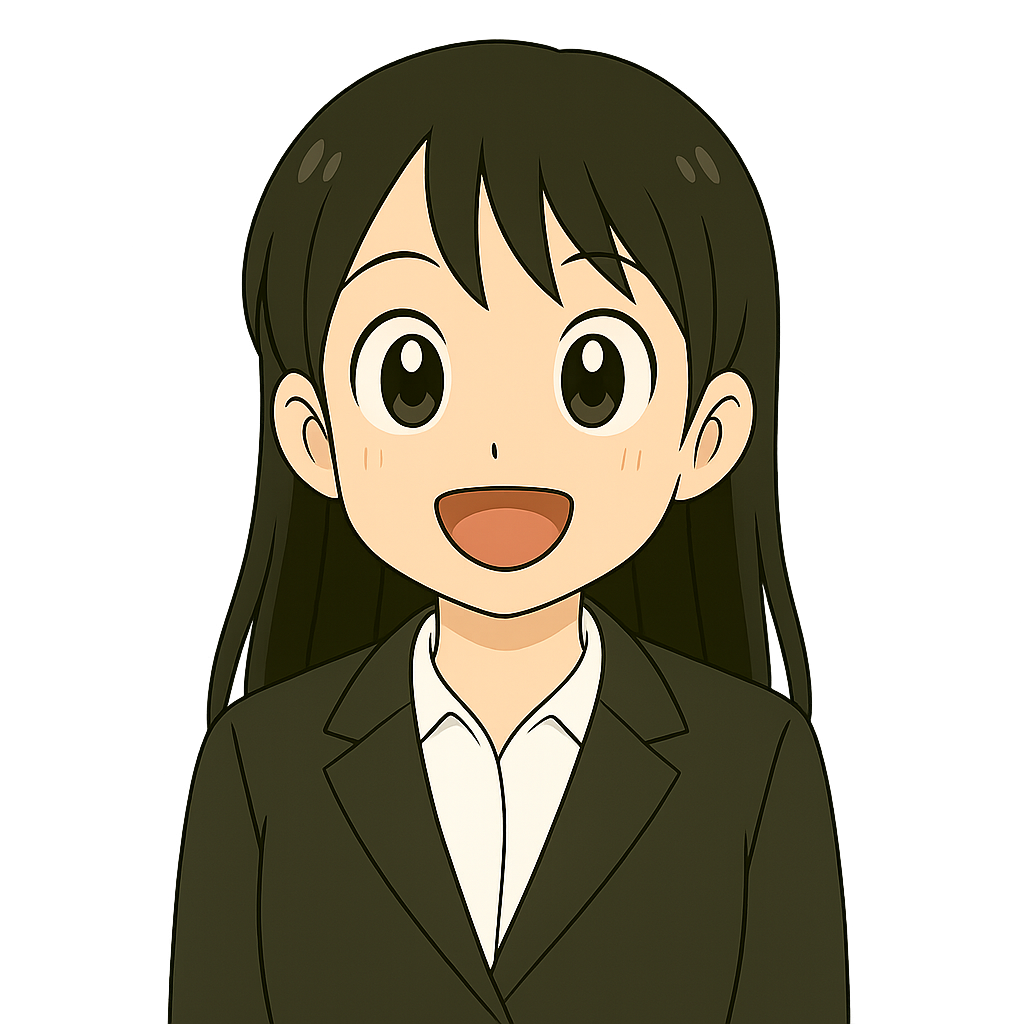
FPの勉強をしていたら「関連法規」って出てきたんだけど、、、これってそんなに大事なんですか~?

実はFPの仕事っていろんな法律に関係してるんだよ。税金のこと話すなら税法、保険のことなら保険業法、、、みたいに!

なるほど~、でも法律って聞くだけで眠くなっちゃう、、、

だよね、気持ちはわかるよ。でもFPは「お金の専門家」だから、間違ったアドバイスをしたら大問題なんだ。だからこそ、どこまでが自分の仕事で、どこから先は他の士業の業務にあたってしまうのか、そういう線引きを法律できちんと理解しておくことが大切なんだよ。

たとえFPが「お金の専門家」でもね、なんでもかんでも説明していいわけじゃないんだよ。
たとえば、顧客から税金の相談を受けても、「この場合の税金はいくらです」とか「こうすれば節税になりますよ」みたいに、個別具体的にアドバイスしちゃうのはダメなんだ。
それ、税理士さんの独占業務だから、うっかりやると法律違反になっちゃうんだよ~。

えぇ~!?でも確かに、もし法律でなんにも縛られずに、税金も保険も投資もぜ~んぶ自由にアドバイスできちゃったら、、、
それってもう、FPって他の士業より圧倒的に凄いスーパー資格になっちゃいますよね~!

そうだね。だからこそ、FPがやっていいこと・やっちゃいけないことをちゃんと知っておくのはすごく大事なんだ。
今回は、「どこまでがFPの仕事の範囲なのか」、そして「どこから先は他の士業の専門分野になるのか」っていうのを、士業ごとにわかりやすく説明していくよ。
FPにも“法律の壁”がある!業務に関わる関連法規
FPは「お金の専門家」として、税金、保険、投資、相続など幅広い分野でアドバイスをしますが、その際に法的な制限があることを理解しておく必要があります。
特に、他の士業(税理士・弁護士・社労士など)の独占業務に触れないよう、法律をしっかり押さえておくことが大切です。
「どこまでが自分の仕事なのか」「どこからは他の専門家にバトンタッチすべきなのか」
この線引きを知っておけば、自信を持って正確な範囲で対応できるようになります。
FPはお金の専門家であるとはいえ、すべての分野を完璧にこなせるわけではありません。
税金には税理士、保険には保険募集人、投資には証券外務員など、それぞれの分野には専門のプロフェッショナルが存在します。
FPに求められるのは、法律の範囲内で適切なアドバイスを行うこと、そして必要に応じて他の専門家の力を借りる柔軟さです。
FPの仕事は決して一人で完結する“個人戦”ではなく、複数の士業が連携して顧客の課題に向き合う“総力戦”。
何でも自分でできると天狗にならず、時には他の士業と手を取り合いながら、最善の解決策を導くことこそが、信頼されるFPとしての姿勢なのです。

うわ~、FPって何でもアドバイスできるわけじゃないんですね、、、ちょっと意外でした~。

やっちゃいけないことを知らずにやると、法律に触れちゃうこともあるから注意が必要なんだよ。

でも実際、どこからがダメなのか、線引きってむずかしいかも、、、
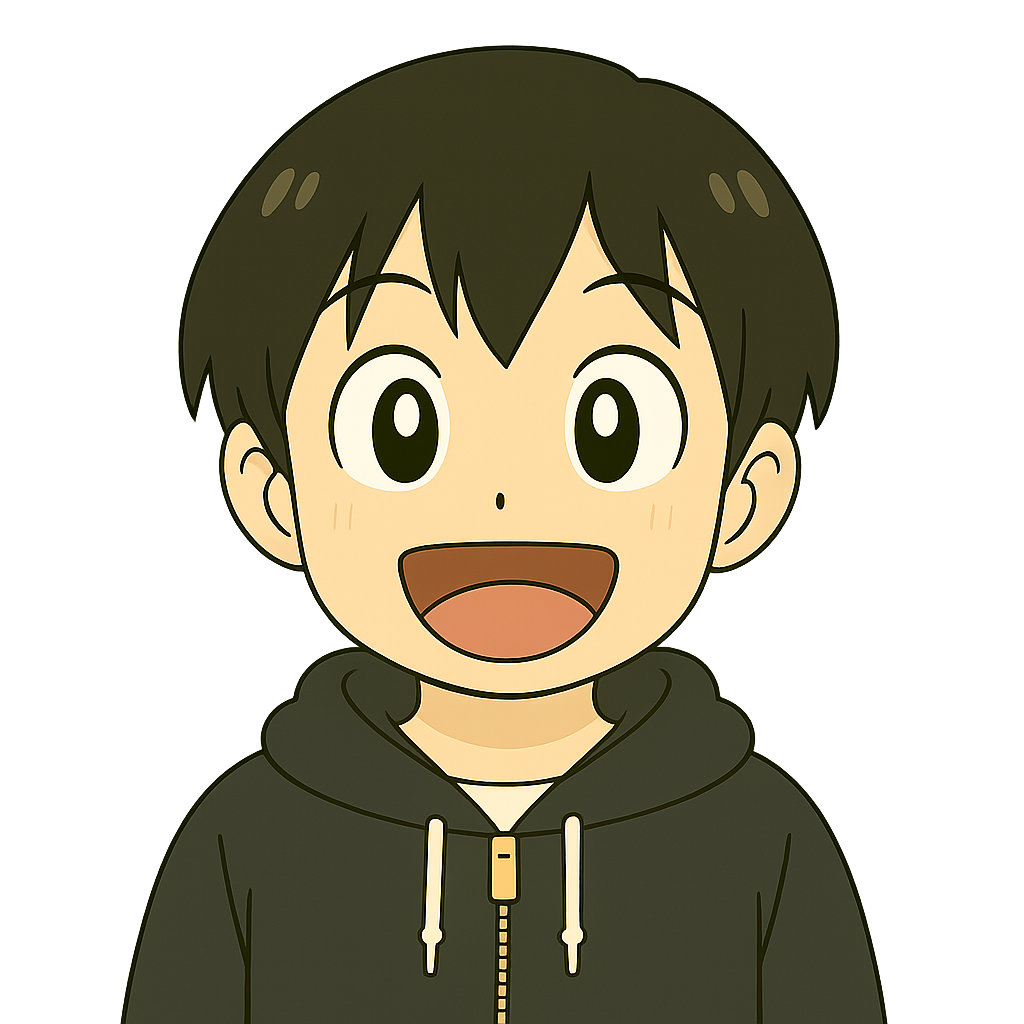
そうだね。じゃあ次は、税理士・弁護士・社労士とか、FPと関わりの深い士業ごとに「何がOKで何がNGか」を具体的に見ていこう!
ここが違う!FPと各士業の仕事の境界線
FPができること・できないことを正しく理解しないと、知らずに法律違反になるリスクも、、、。
そこで、以下ではFPと他の士業との仕事の境界線を「OK」「NG」に分けて、わかりやすく整理していきます。
FPと税理士の業務の違い|OK・NG一覧表
| 内容 | FPがやってOK ✅ | FPがやるとNG ❌(税理士の業務) |
|---|---|---|
| 税制の説明 | 一般的な税制の仕組みや制度を説明する(例:所得税の基本ルール、控除の種類) | 個別具体的な税額の計算を行う(例:あなたの所得税は〇〇円です) |
| 税務相談 | 税制の一般的な考え方や優遇制度を紹介する | 個別の節税対策を提案する(例:この方法なら節税できます) |
| 確定申告 | 確定申告の必要性や一般的な手順を案内する | 申告書の作成や代理提出をする |
| 節税アドバイス | 節税制度(NISA、iDeCoなど)を制度として紹介する | 顧客の具体的な数字をもとに節税額を試算・提案する |
| 相続対策 | 一般的な相続対策の考え方(遺言、贈与など)を伝える | 遺産の評価や分割に関する具体的な税務指導を行う |
FPと税理士の業務の違いを分ける重要キーワードは「個別具体的」であり、顧客の具体的な相談内容や金額にまで踏み込んで計算や助言を行うのはNG。
FPにできるのはあくまで一般的な範囲内、たとえ相談を受けたとしても過去の事例などを使って説明する程度に留める必要があります。
補足ポイント
- 税理士法 第52条により、**税務代理・税務書類の作成・税務相談(具体的なもの)**は税理士の独占業務です。
- FPは、制度の一般論を伝える「ナビゲーター的立場」に徹することが重要です。
- 確定申告や、年末調整に関するセミナーは開催してok
- 有償・無償問わず、税理士の独占業務は行うことができない。
FPと弁護士の業務の違い|OK・NG一覧表
| 内容 | FPがやってOK ✅ | FPがやるとNG ❌(弁護士の業務) |
|---|---|---|
| 法律制度の説明 | 遺言、相続、離婚、借金問題などの制度や手続きの一般的な説明 | 顧客の具体的な事情を聞いたうえで法的な助言や解決策を提示する |
| 契約書関連 | 契約書の基本構成や一般的なポイントを紹介する | 契約内容のチェックや修正案の提示をする(法的アドバイスに該当) |
| トラブル対応 | 紛争時に弁護士など専門家に相談すべき状況を案内する | 顧客の代わりに交渉や和解の提案を行う(非弁行為に該当) |
| 遺言・相続対策 | 遺言の種類や一般的な活用法を紹介する | 遺言書の作成指導や文案の作成を行う |
| 借金・債務整理 | 債務整理の仕組みなどを制度として紹介する | 具体的な返済計画や債権者との交渉内容を提案する |
FPと弁護士の業務の違いは、ここでも「一般的な説明に留めるか、それとも個別具体的な助言になるか」が明確な境界線となっており、法的判断や解決策の提示といった弁護士の独占業務に踏み込まないよう十分な注意が必要です。
また、下記は弁護士業務と誤解されやすいけれど、実はFPでもできる行為です。
公正証書遺言作成時の「証人」
よくある誤解:
「遺言に立ち会うなんて、法律の専門家じゃないと無理でしょ?」
→ 実は、特別な資格は不要です!
ポイント:
- 公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必要(公証人法第26条)
- 弁護士や司法書士である必要は一切なし
- 一般の人でも、一定の条件を満たせば証人になれる
任意後見契約の「受任者」について
よくある誤解:
「後見人って法律の専門家じゃないとダメなんじゃないの?」
→ これも一般の人でOKなんです!
ポイント:
- 任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて、信頼できる人と契約を交わす制度
- 受任者(後見を受ける人)は弁護士・司法書士である必要なし
- 親族、友人、FPなど、本人が信頼している人であれば契約可能
補足ポイント
- 弁護士法 第72条により、法律事務の取り扱いは弁護士の独占業務です。
- FPは「制度の解説や一般的な情報提供」にとどめ、法的判断や解決方法の提案はしないことが大切です。
- 相続に関連するセミナーは開催してok
- 有償・無償問わず、弁護士の独占業務は行うことができない。
FPと社会保険労務士の業務の違い|OK・NG一覧表
| 内容 | FPがやってOK ✅ | FPがやるとNG ❌(社労士の業務) |
|---|---|---|
| 公的年金制度関連 | 年金の種類や仕組み、受給条件などの一般的な制度説明 | 顧客の具体的な情報を基にした年金の受給額の計算や申請手続きの代行 |
| 労働保険・社会保険関連 | 雇用保険や健康保険の概要・仕組みの解説 | 加入手続きや給付請求の書類作成・申請代行 |
| 就業規則や労務管理 | 一般的な労働時間制度などの制度的な説明 | 就業規則の作成・変更・提出代行や個別企業の労務相談 |
| 働き方・ライフプラン相談 | 「働き方と年金の関係」「退職後の備え」などの生活設計に基づく一般的な助言 | 雇用契約や労働条件に関する具体的な相談や交渉アドバイス |
FPと社会保険労務士の業務の違いも、ここでも一般的な説明(仕組みや制度)に留めるか、それとも個別具体的な内容に踏み込むかが明確な境界線となります。
また、下記は社労士業務と誤解されやすいけれど、実はFPでもできる行為です。
「ねんきん定期便」を使った年金試算は、FPもできる!
よくある誤解:
「年金の受給額を計算するのは社労士の独占業務なんじゃ?」
→ 実は、資料を元にしたシンプルな試算ならFPでもOKです!
FPができる年金試算の範囲
- 「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」に記載された情報(加入履歴・納付額など)をもとに、一般的なルールに当てはめて見込み額を計算する。
- 計算結果は、あくまで参考値として提示し、「正式な金額ではありません」と説明する
- 制度の仕組みや考え方をセットで伝える(例:「年金は60歳からの繰上げ受給は減額し、66歳以降に繰下げると増額する」など)
補足ポイント
- 社会保険労務士法第27条により、社労士は社会保険手続きや労務管理の書類作成・申請代行・相談業務を独占しています。
- FPは、制度全体の理解を助けるナビゲーター的な役割に徹し、具体的な申請や個別指導には踏み込まないことが重要です。
- 有償・無償問わず、社労士の独占業務は行うことができない。
FPと保険業の業務の違い|OK・NG一覧表
| 内容 | FPがやってOK ✅ | FPがやるとNG ❌(保険募集人の業務) |
|---|---|---|
| 保険の種類や仕組みの説明 | 医療保険・生命保険・損害保険などの一般的な仕組みや特徴の説明 | 特定の保険会社の商品を紹介・提案する |
| 保険の必要性についての助言 | 「家族構成や収支に応じて保険の備えは大切」といったライフプランに基づく一般的なアドバイス | 「この商品がおすすめです」「この保険に入りましょう」と特定商品の勧誘や推奨 |
| 保険料の試算 | 保険料の考え方や一般的な相場を紹介する | 特定の保険商品での保険料シミュレーションや設計書の提示 |
| 契約や手続き | ― | 契約申込書の記入・提出など、契約にかかわる一切の行為 |
| 商品比較 | 複数の保険商品の特徴や制度上の違いを比較する | 特定会社の商品を比較して優劣をつけるような説明(募集行為に該当) |
FPは「保険を売る人」ではなく、「保険を考えるための整理と気づきをサポートする人」。
保険に関する一般的な説明や、見直しの考え方のアドバイスは可能ですが、保険募集人のように特定の商品を勧めたり、契約に結びつける行為はできません。
補足ポイント
- 保険業法第276条により、保険契約の募集に従事する者は、内閣総理大臣の登録を受けた保険募集人でなければならない。
- 保険業法では、保険募集人資格がない人による保険商品の勧誘や募集行為は違法とされています。
- FPは「保険の制度・考え方・選び方」を伝える立場であり、具体的な商品提案や販売行為はできません。
FPと金融商品取引業の業務の違い|OK・NG一覧表
| 内容 | FPがやってOK ✅ | FPがやるとNG ❌(金融商品取引業に該当) |
|---|---|---|
| 金融商品の種類や制度の説明 | NISAやiDeCo、投資信託の仕組みなど、制度的・一般的な説明 | 特定の投資信託や株式を具体的に勧める・推奨する |
| 資産運用の考え方・リスク管理の基本 | 長期分散投資、ドルコスト平均法などの投資手法の紹介 | 「このファンドが利益出ますよ」など、投資判断を助言する行為 |
| 金融商品の比較 | 「株は価格変動が大きい」「債券は安定性がある」などリスクの特性の紹介 | 特定商品の収益率や手数料を比較して優劣をつけるような説明 |
FPは、株式・債券・投資信託といった金融商品の基本的な特徴や仕組みの説明、およびNISAやiDeCoなどの税制優遇制度に関する一般的な解説を行うことができます。
一方で、具体的な金融商品の販売や勧誘、銘柄を指定した投資助言、代理行為(顧客に代わって取引を行うこと)は、金融商品取引法により、登録を受けた金融商品取引業者や投資助言業者のみが行える業務であり、FPが行うことはできません。
補足ポイント
- 金融商品取引法により、「投資助言・代理業」や「第一種・第二種金融商品取引業」には登録が必要です。
- FPが有償・無償を問わず、個別の投資商品について勧誘・助言を行うと法律違反になる可能性があります。
まとめ:FPは一人じゃない。チームで支える“総力戦”という考え方

はぁ〜、なんとなく「FPってお金のことなら全部答えられなきゃ」って思ってたけど、
実はちゃんと線引きがあるんですね~。やりすぎると違法になるなんて、、、こわっ。

FPは万能っぽく見えるけど、税金は税理士、法律は弁護士、年金手続きは社労士って、
それぞれの“専門エリア”がちゃんとあるから、そこを越えないのが大事なんだよ。
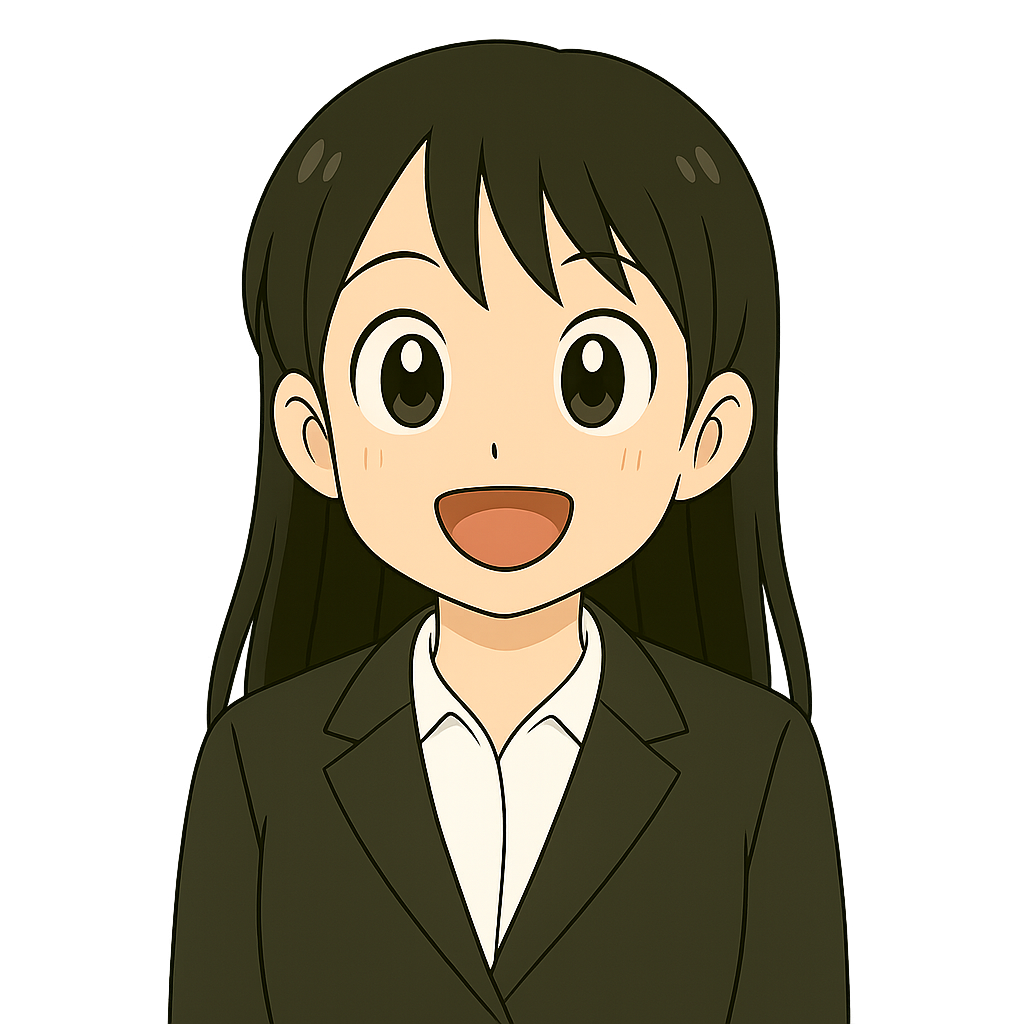
今回の話でそれぞれの士業の仕事範囲がちゃんとわかって、すごくスッキリしました~♪
でも、こうやって線引きがあるって知ってても、やっぱり少しでも知らないと、うっかり踏み込んじゃいそうですよね~。
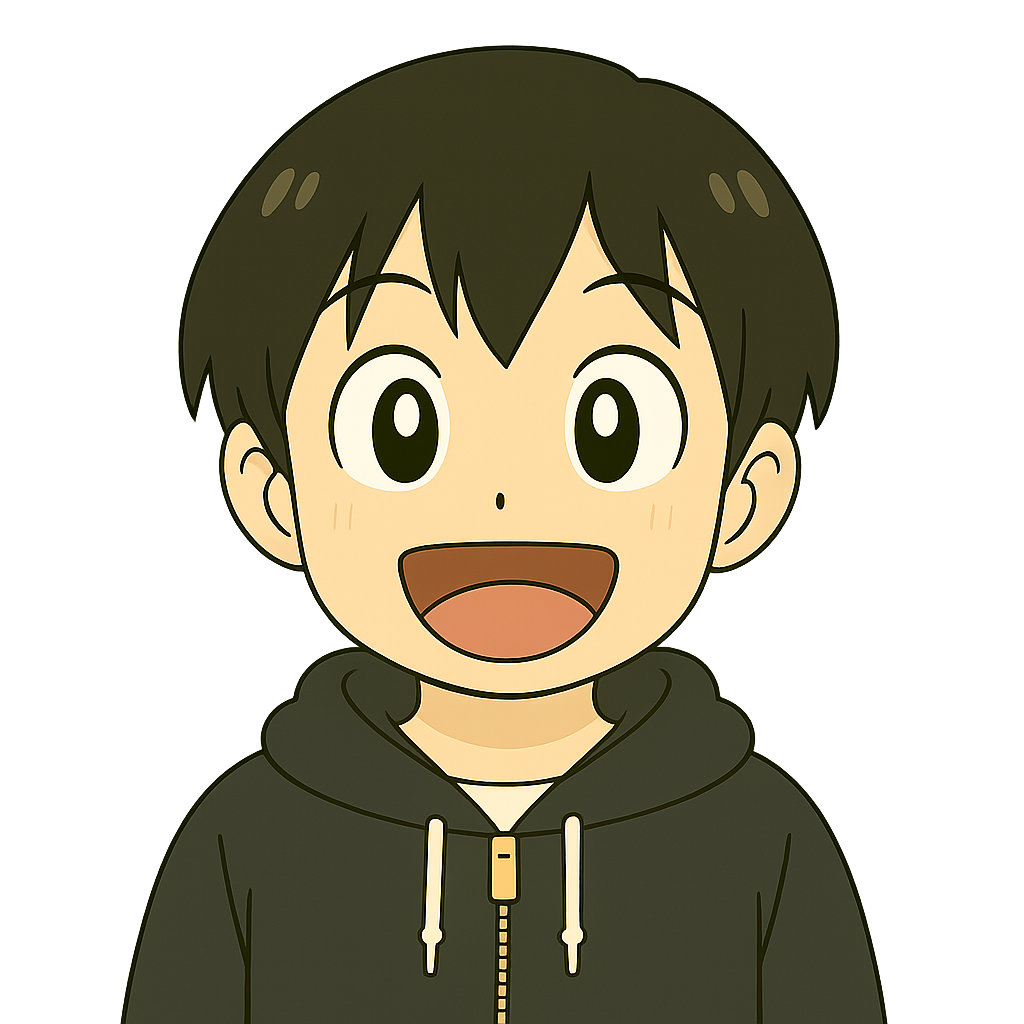
うん、だからこそ「自分はどこまでできるか」と「ここから先は誰に相談すべきか」って判断できることが、
信頼されるFPになるための第一歩なんだよ。

なるほど~、FPって“なんでも屋”じゃなくて、“つなぎ役”って感じなんですね!
最後に:FPかしの独り言
今回はFPの仕事範囲と各士業の仕事範囲(独占業務)について解説しました!
FP(ファイナンシャル・プランナー)には、医師や弁護士のような「独占業務」がありません。つまり、極端に言えば、FPの仕事は資格がなくてもできちゃいます。
それでもなお、FP資格を持っていることで得られる「信用」や「専門家としての付加価値」は大きく、相談者からの信頼にもつながります。
個人的には、「一家に一人FP資格保持者」ぐらいが理想だと思っています(笑)。
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】