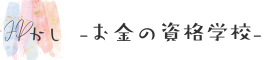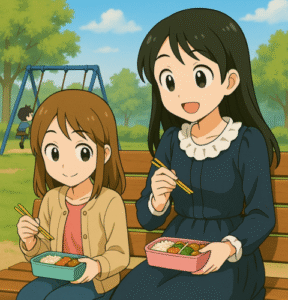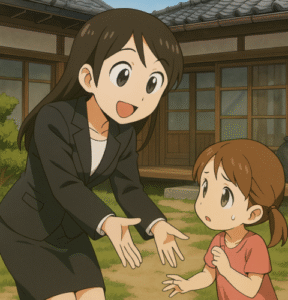なんで同じ土地なのに評価額が違うの?固定資産税と相続税のナゾを解説!
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】
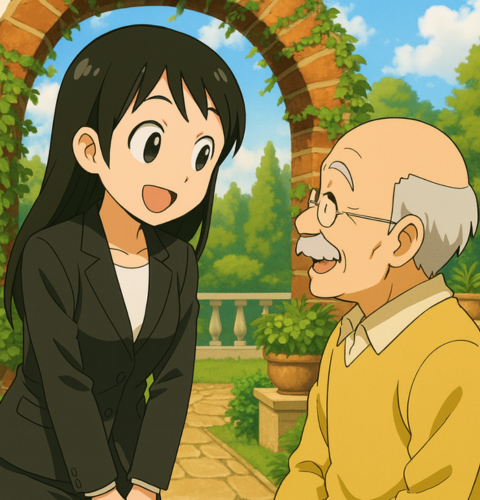

土地の価格ってさ、固定資産税の評価とか相続税の評価で割合変わるじゃん?あれなんで?土地は土地じゃん!

それ、ほんと変だよね。同じ土地なのに評価がバラバラって、どう考えてもおかしくない?
でもね、実は税金ごとに“ちょうどいい負担”になるように評価のしかたを変えてるんだ。

ちょうどいい負担!?なにそれ、もっと詳しく教えてー。

おっ、きりちゃん乗り気になってきたね~。
じゃあ今回は、なんで同じ土地なのに評価額が違うのか?について、わかりやすく解説していくよ!
目次
固定資産税と相続税で評価が違うのは“税の負担調整”のため!
土地の価格って、本来「一つだけ」のように思えますよね。
でも実は、税金の種類によって“わざと違う金額”で評価されているんです。
まずは、土地の評価額がどのように使い分けられているのかを確認してみましょう。
| 価格の種類 | 評価の目的 | 評価割合の目安 |
|---|---|---|
| 公示価格 | 一般的な土地の基準価格 | 100% |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税・都市計画税の計算 | 約70% |
| 相続税評価額(路線価) | 相続税・贈与税の計算 | 約80% |

やっぱり固定資産税評価とか相続税評価って、普通の価格より低くなってるんだ~!っで、なんでなの…?
どうしてそんなことをするのかというと、理由はズバリ――
👉 税金の負担を調整するため!
たとえば、固定資産税は毎年かかる税金。
もしこれを実際の市場価格そのままで計算してしまうと、税金が重くなりすぎてしまうんです。
だから評価額を少し低めに設定して、負担が大きくなりすぎないようにしているんですね。

固定資産税は毎年かかるからね。毎回100%の評価で課税されたら、負担が重すぎるんだよ。
一方、相続税は一生のうちに何度もかかるわけではない税金です。
そのため、ある程度は実際の価値に近い金額で評価しようとする傾向があります。
でもやっぱりこれも、“少し軽め”の評価にして、税負担を調整しているんです。

なるほど〜、だから固定資産税評価より相続税評価の方がちょっと高めなんだ!
でも100%だったら“そんなの払えないよ~”って文句出そうだし、
80%くらいにして、うまくバランス取ってるってことなんだね!

そうそう、よく気づいたね。
100%にすると不満が出るし、低すぎても不公平になる。だから相続税評価は、そのちょうど中間くらいで調整されてるんだ。
つまり評価額がバラバラなのは、いいかげんに決めてるのではなく、
「誰にとっても納得できる税負担」にするための仕組みなんですね。
評価額だけじゃない!税額がグッと下がる特例の話

とはいえ、70%とか80%にしたって、土地ってやっぱりまだまだ高いよ~💦

まあ、たしかにそれはあるね。
でも安心して、固定資産税も相続税も、評価額からさらに軽減される“特例”が用意されてるんだ。
条件に当てはまれば、かなり税額が下がることもあるんだよ。
実は、固定資産税や相続税は「評価額」だけでそのまま税金が決まるわけではありません。
一定の条件を満たすと、評価額からさらにグッと減額される仕組みがあるんです。
固定資産税の主な軽減措置
- 住宅用地の特例
→ 自宅の土地については、最大で評価額の1/6まで軽減されることも! - 新築住宅の建物部分の減額
→ 一般住宅は3年間、長期優良住宅は5年間、固定資産税が1/2に

たとえばだけど――
評価額が1,200万円の土地があったとするよね。
これが住宅用地として使われていれば、課税標準額は1/6に軽減されるんだ。
つまり、200万円まで下がるってこと。
相続税の主な軽減措置
- 基礎控除
→ 3,000万円+600万円×法定相続人の数までは非課税 - 小規模宅地等の特例
→ 一定の条件を満たせば、宅地の評価額が最大80%減額されることも!

相続税でも、うまく使えばグッと下がる特例があるよ。
たとえば、自宅の土地が5,000万円の評価額だったとするよね。
でも、『小規模宅地等の特例』を使えば、最大で80%減額されるから、
👉 5,000万円 → 1,000万円になることもある。
しかもこれは“評価額”が下がるから、そのぶん課税される金額もガクッと減るってわけ。
こうした特例があるからこそ、評価額を見て「高すぎる…」と感じても、実際の税額は意外と抑えられているケースが多いんです。
土地の評価がバラバラなのは、“税金ごとの役割”が違うから

そっか〜、土地の評価がバラバラなのって、税金ごとに役割が違うからなんだね。なんか納得かも。

そうそう。毎年払う固定資産税は負担が大きくなりすぎないように、
相続税は公平に資産を引き継ぐためにって、それぞれちゃんと意味があるんだよ。

バラバラに見えても、その税金にとって“ちょうどいい”評価が選ばれてるんだ。
制度って、ただ複雑なだけじゃなくて、意外とよく考えられてるんだよ。
土地の評価額が税金によってバラバラなのは、決して適当なわけではありません。
それぞれの税金が持つ目的や負担の性質に合わせて、「ちょうどいい評価額」が設定されているんです。
固定資産税は毎年かかるからこそ軽めに、相続税は公平性を重視してやや高めに。
そして、それだけでなく、実際の税額を下げるための特例もしっかり用意されています。
制度の背景を知れば、「なんで違うの?」という疑問も「なるほど、そういうことか」と納得に変わるはずです。
「お金の教養をもっと深めたい」「FPの知識を実生活に活かしたい」そんな方には、
社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!
金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!
7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】